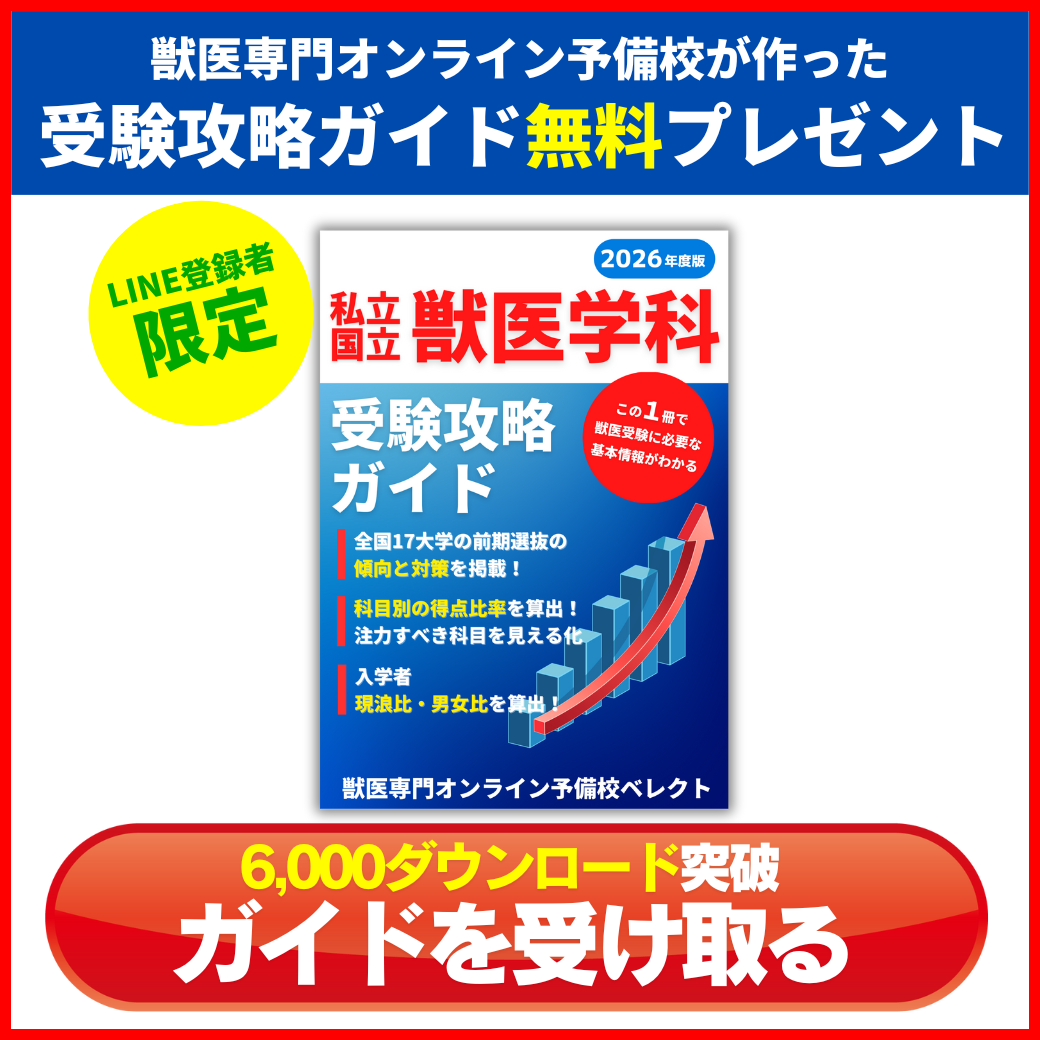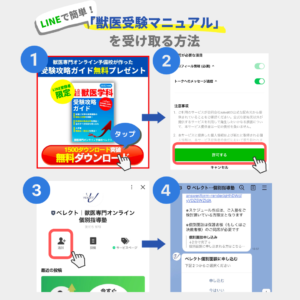こんにちは!獣医専門オンライン予備校のベレクトです。
2026年度東京農工大学共同獣医学科の一般選抜に向けて、合格点の目安や教科ごとの傾向が気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、北大獣医学部の一般選抜において求められる得点ラインや、英語・数学・理科の出題傾向について、過去問と合格点の分析をもとに詳しく解説します。
担当するのは、当塾講師として受験指導に携わる現役の獣医学部生。
自身の体験をふまえながら、効果的な勉強法までわかりやすくお伝えします。
東京農工大学共同獣医学科を目指す受験生は、ぜひ参考にしてください!
- 共テの点数が圧縮されないため、共テが非常に重要&ハイレベル
- 後期は英語1科目のみ。英語を圧倒的に得点源とできないと厳しい
- 前期日程は年々、倍率が上がっている
- 各科目の入試傾向と勉強法を解説しました(2021年度~)
北海道大学 獣医学部 3年生。当予備校の講師として活躍中。
前期試験で現役合格(共通テストで8割超え)を果たし、ベレクトは数学・生物・化学・英語を指導。これまでに北海道大学など、複数の獣医学部合格者を輩出しています。
自身の受験経験と豊富な指導実績をもとに、最新の入試傾向の分析や、実践的な勉強法について、当サイトのコンテンツ執筆にも携わる。
(2025年 執筆時)
2026年度 東京農工大学共同獣医学科「一般選抜」の入試科目・必要科目おさらい
一般選抜前期
| 内容 | |
|---|---|
| 募集人数 | 25名 |
| 試験内容 | ・共通テスト ・個別学力検査 |
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) 【社会】100点 【国語】200点 【外国語】200点 ※英 独 仏 中 韓から1科目 【数学】200点 【理科】200点 ※物理 化学 生物から2科目 【情報】50点 |
| 個別学力検査 | 3教科4科目(700点満点) 【英語】200点 【数学】200点 【理科】300点 ※物理 化学 生物から2科目 |
一般選抜後期
| 内容 | |
|---|---|
| 募集人数 | 6名 |
| 試験内容 | ・共通テスト ・個別学力検査 |
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) 【社会】100点 【国語】200点 【外国語】200点 ※英 独 仏 中 韓から1科目 【数学】200点 【理科】200点 ※物理 化学 生物から2科目 【情報】50点 |
| 個別学力検査 | 1科目(400点満点) 【英語】400点 |
共通テストは情報を除いて素点が点数になります。
農工大は獣医系では北大と並ぶと難関大学と言われていますが、北大は共通テストの点数が圧縮されるのに対して農工大はされないので、農工大において共通テストは非常に重要かつハイレベルであることがわかります。前期日程は数学と英語の方が理科よりも科目あたりの点数が若干高くなります。
後期日程は英語1科目のみです。定員は僅か6名かつ1科目のみで400点満点なので英語を圧倒的に得点源とできない限り難しいでしょう。
【分析】合格にはどれくらいの得点が必要?
東京農工大学の直近の倍率、合格最低点は以下のようになります。
※2024年度以前は共通テストの情報が含まれていないため1650点満点が1600点満点、1350点満点が1300点満点になります。
| 年度 | 合格最低点・合格倍率(受験者数/合格者数) |
|---|---|
| 2025年 | 【一般前期】合格最低点:1248/1650 合格倍率:4.7倍 【一般後期】合格最低点:1055/1350 合格倍率:10.4倍 |
| 2024年 | 【一般前期】合格最低点:1189/1600 合格倍率:5.8倍 【一般後期】合格最低点:1071/1300 合格倍率:15倍 |
| 2023年 | 【一般前期】合格最低点:1170/1600 合格倍率:4.8倍 【一般後期】合格最低点:1037/1300 合格倍率:8.1倍 |
| 2022年 | 【一般前期】合格最低点:1133/1600 合格倍率:4.3倍 【一般後期】合格最低点:1003/1300 合格倍率:8.4倍 |
| 2021年 | 【一般前期】合格最低点:1166/1600 合格倍率:4.6倍 【一般後期】合格最低点:1009/1600 合格倍率:5.1倍 |
| 2020年 | 【一般前期】合格最低点:1146/1600 合格倍率:3.9倍 【一般後期】合格最低点:1126/1600 合格倍率:8.8倍 |
前期日程は年々倍率が高くなり、2024年には6倍に迫る競争率でした。
農工大は、東京のアクセスの良いエリアにありながらも広いキャンパスと落ち着いた環境が保たれ受験生から人気が高いです。首都圏住みの人にも上京する人にもぴったりですね。
なお2025年は、前年度よりは若干競争が落ち着いた印象です。共通テストが新課程に変化し共通テスト分の配点が上がった分、出願前のリサーチで慎重になったのかもしれません。(なお現浪比は毎年ほぼ変わっていません。)
とはいえ、依然4倍以上あるためハイレベルな戦いでしょう。合格最低点を見ても7割5分をとる必要があります。
後期日程は受験者数/合格者数で見ても、倍率が8倍を超えており、非常に厳しい競争になっています。合格者最低点を見ると1000点前後ですが、前期日程と後期日程で総合得点が300点異なるのに合格最低点が100点ほどしか違わないのを見るとそのレベルの高さが分かります。
【教科別】個別学力試験の平均点(大学公表)
東京農工大学が公表している各年度の個別学力試験(前期日程)の平均点を以下にまとめました。(小数点以下四捨五入)
| 年度 | 数学 | 英語 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 162/200 | 127/200 | 205/300 |
| 2024年 | 128/200 | 123/200 | 229/300 |
| 2023年 | 136/200 | 117/200 | 226/300 |
| 2022年 | 140/200 | 149/200 | 205/300 |
| 2021年 | 99/200 | 156/200 | 183/300 |
| 2020年 | 119/200 | 155/200 | 191/300 |
平均点
どの科目も年によって変動がありますがおおよそ6割強が平均点となっています。農工大の試験問題は北大ほど高得点率を期待できるものではないので取れる問題を手堅く抑えることが重要です。
2025年の傾向
2025年は数学が易化したことで数学で差がつかなくなり、数学を武器としていた受験生は苦労したと思われます。
先程紹介した通り共通テストと個別学力試験の合計点の合格最低点すら7割5分なので、余裕を持って平均で合格するには共通テストで9割前後獲得してく必要があると言えるでしょう。
【教科別】合格点や過去問から入試の傾向と勉強法を解説
ここからは、各教科の出題傾向とそれに合った勉強法を解説していきます。
各教科の出題傾向は、受験人数が多い前期入試を基に分析を行いました。
数学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:ベクトル 大問2:三角関数 大問3:媒介変数 速度と加速度 大問4:媒介変数 積分 |
| 2024年 | 大問1:ベクトル 大問2:数列 大問3:微分 大問4:微分 積分 |
| 2023年 | 大問1:複素数平面 大問2:数列 大問3:微分 積分 大問4:積分 |
| 2022年 | 大問1:複素数平面 大問2:数列 大問3:微分 大問4:微分 積分 |
| 2021年 | 大問1:ベクトル 大問2:数列 大問3:微分 極限 大問4:積分 |
| 2020年 | 大問1:ベクトル 図形と方程式 大問2:数列 大問3:三角関数 微分 積分 大問4:微分 積分 |
試験時間は120分で大問は4つです。1問に30分弱かけられる計算ですが時間配分には気をつけましょう。
問題構成
出題傾向として大問2以降は毎年数学Ⅲレベルの微分積分と数列が出されています。また大問1はベクトル(図形と方程式の問題とも解釈できるがベクトルで解かないと大変)か複素数平面のどちらかが出題されています。これらの単元をよりしっかりと勉強することは必須でしょう。
難易度
問題の難易度は標準的と言われていますが、方針が立ちやすくても計算量が多かったり証明を求められたりと練習を積んでいないと手間取る問題が多いです。そのため先述した通り1問あたり30分かけられる計算ですが、決して時間に余裕があるとは言えないでしょう。
ただし2025年度のように問題が非常に平易になることもあります。問題が簡単な場合、周囲と差をつけることができないので数学に限らず1つの科目にヤマを張るのは避けましょう。
対策
対策として教科書傍用問題集や網羅系参考書を繰り返し解き、基本的な解法を身に着けたうえで入試問題集や過去問を演習を何度も行い、考えながら手を動かす練習をすることが求められます。標準的な問題とはいえ合格最低点からもわかる通り高得点を狙わないといけません。実力が付く前にやみくもに過去問を解くのではなく土台を固めてからアウトプットの場として入試問題や過去問演習を行いましょう。
英語
前期の出題傾向
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 2025年8月現在非公開 |
| 2024年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:会話文 |
| 2023年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:会話文 |
| 2022年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:会話文 |
| 2021年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:会話文 |
| 2020年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:会話文 |
試験時間は60分で大問は3つです。
問題構成
毎年大問2つが読解問題、1つが会話文を受けた小問や英作文になっています。
難易度
読解問題の難易度は標準的で比較的読みやすいと言われていますが、テーマが幅広く自分が知らない領域について出された場合丁寧に読み解けるかが重要になります。設問形式は内容真偽や内容説明、英文和訳、語彙など基本的なものです。
会話文を踏まえた記述問題は簡潔に書ききる能力が求められます。北大の英作文と比べて字数が少ないからこそ必要なポイントを押さえた記述ができるかがカギです。冠詞や前置詞などのミスは許されないので、学校や予備校の先生に添削してもらうようにしましょう。
対策
対策としては英文法をマスターしたうえで、長文を沢山読むように心がけましょう。英語は一朝一夕に早く読めるようになるものではないので普段からの積み重ねが受験学年になったときに生きてきます。受験が近づいたら英作文を中心に過去問演習を行い農工大の出題形式に慣れましょう。
理科
化学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:理論 大問2:無機 理論 大問3:有機 大問4:理論 有機 |
| 2024年 | 大問1:理論 大問2:無機 大問3:有機 大問4:有機 |
| 2023年 | 大問1:理論 無機 大問2:理論 大問3:有機 大問4:理論 無機 |
| 2022年 | 大問1:理論 大問2:無機 大問3:有機 理論 大問4:有機 |
| 2021年 | 大問1:理論 大問2:無機 大問3:有機 大問4:有機 |
| 2020年 | 大問1:無機 大問2:理論 大問3:無機 大問4:有機 大問5:有機 |
試験時間は理科2科目で160分で大問は4つ(2020年だけ5つ)です。計算量が多く応用力も試されるため時間はかなりシビアでしょう。
難易度
難易度は標準的と言われていますが、年によって変動があります。問題集でよく見るような典型的な問題が出されることもあれば初見の反応を与えられた情報をもとに論理的に解答する問題もあります。年によっては無機化学も有機化学も教科書でなじみのないものが出題され、(落ち着いて解ければよいのですが)知らないものが出てもパニックにならないことも重要でしょう。
理論化学をマスター
理論化学が重要視される傾向にあり、無機化学有機化学の融合問題として出題されていることが多いです。化学で必要な公式や化学反応式、原理を暗記することは大前提です。しかし暗記したとしても応用を問われたとき手間取る人が多いです。
範囲にとらわれずに勉強を
例えば普段勉強する時、教科書の順番に従って、ある程度範囲が定まった「章」や「節」の中で繰り返し問題演習をする人が大半だと思います。最初の内はそれでよいのですがずっとそれをやっていてもそれは「ある枠組のなかでの記憶」ということになります。農工大レベルともなると教科書そっくりの内容を問われることは少なく、ある程度アレンジが入ります。
その際、今まで学習したものの中からどの知識を使うか、学んでいたことが別の枠組のなかではどのように生きてくるのか気づきながら演習を行えると試験を突破するのに相当な力が付くでしょう。
対策
対策として教科書の内容を完璧にしたうえで幅広く問題演習を行いましょう。過去問や同様の傾向の国立大学の問題など初見の事柄に対して冷静に対処することが重要です。また年によっては論述が課されることもあるため、キーワードを押さえた記述ができるよう理屈で考える習慣をつけましょう。
物理
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:力学 大問2:熱力学 大問3:電磁気 |
| 2024年 | 大問1:力学 大問2:波動 大問3:電磁気 |
| 2023年 | 大問1:力学 大問2:熱力学 大問3:電磁気 |
| 2022年 | 大問1:力学 大問2:電磁気 大問3:波動 |
| 2021年 | 大問1:力学 大問2:電磁気 大問3:熱力学 |
| 2020年 | 大問1:力学 大問2:波動 大問3:電磁気 |
試験時間は理科2科目160分で大問は3つです。
難易度
力学、電磁気は必ず出題され年によって波動または熱力学が出題されます。問題の難易度は標準レベルですが他もう1つ理科があることを考慮すると素早い処理能力が求めれられるでしょう。
得点のために
教科書に書かれている事象や公式は完璧にし、普段から手を動かすことを心がけましょう。化学や生物よりも科目の大問数が少ないので、問題の途中で分からなくなったり、勘違いや計算ミスをすると後に大きく響くかもしれません。確実な計算力を身につけましょう。
対策
対策として自分で図を書いて演習を行うと良いでしょう。流石に本番は自分で図を描き直すのではなく問題の図の上に矢印などを書き込むことと思いますが、図に慣れておくことで多少見慣れないものが出てきてもその機構を理解しやすくなります。
生物
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:免疫 大問2:細胞生理学 呼吸 大問3:動物の組織 発生 大問4:生態系 遷移 |
| 2024年 | 大問1:体内環境 大問2:動物の反応 大問3:遺伝情報 大問4:生態 |
| 2023年 | 大問1:体内環境 大問2:動物の反応 大問3:不掲載 大問4:不掲載 |
| 2022年 | 大問1:体内環境 大問2:植物の反応 大問3:発生 大問4:植物の代謝 |
| 2021年 | 大問1:植物の生殖 遺伝 大問2:遺伝情報 大問3:動物の反応 大問4:生態 |
| 2020年 | 大問1:進化・系統 大問2:遺伝情報 大問3:体内環境 大問4:生態 |
試験時間は理科2科目で160分で大問は4つです。
問題構成
出題傾向としてニューロン、環境や生態、植物が頻出です。遺伝情報や体内環境も何を問われても大丈夫なよう万全に対策する必要があるでしょう。
設問形式は単語を埋めるものから論述、与えられたデータの考察と多岐に渡ります。単語は教科書に出てくるものはもちろん、時折生物史(生物学に貢献した人や実験についての歴史)にも触れられているので資料集などを一読しておくとよいでしょう。論述問題は事象や原理をキーワードを押さえて簡潔に書くことが求められますが時に100字程度の問題が出題されることもあります。自分で説明できるかを念頭に学習を進めましょう。
対策
対策としては早めに農工大の出題傾向をつかみ、過去問や似た傾向の問題を多くこなすようにしましょう。生物の問題集はたくさんありますが、収録されている問題によっては全く傾向や趣旨(特に医学科の生物や理系私立の生物)がことなり参考書を完璧にすることが必ずしも最善とは言えません。
知っている実験のレパートリーを増やす目的で1周はするべきでしょうが化学や物理ほど1つの問題を何度も解くのではなく、知識が定着したら柔軟に勉強しましょう。国立大学の前年度の過去問が集められている問題集があるのでその中から地方国公立レベルの問題をピックアップ解くと演習量増加につなげられます。
まとめ
今回は東京農工大学の出題傾向および対策についてご紹介しました。
農工大は北大と並ぶ獣医学入試の最難関であり、その立地の良さからも非常に人気で倍率が高いです。
国立大学なので標準的な問題が多いとはいえ、同様に難関と言われている北大と傾向が異なる部分もあり勉強方法も当然異なってきます。
農工大は難関大でありながら傾向や対策についての情報が少なめなので、本記事を読んで少しでも参考にしていただければ幸いです。
-3.png)