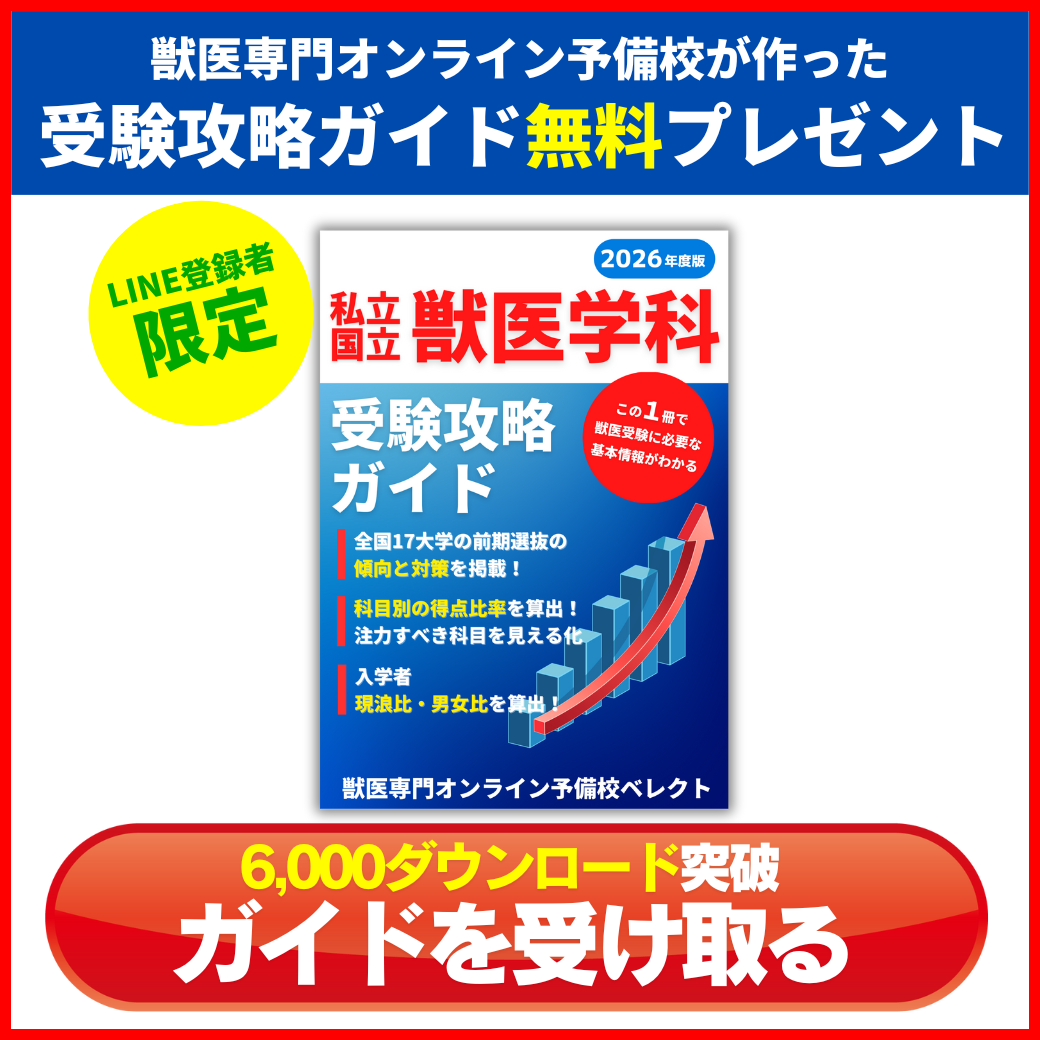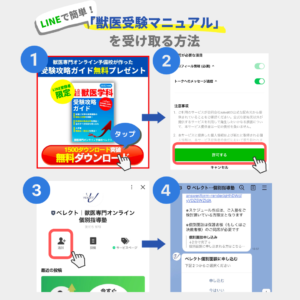こんにちは!獣医専門オンライン予備校のベレクトです。
2026年度鹿児島大学共同獣医学科の一般選抜に向けて、合格点の目安や教科ごとの傾向が気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、北大獣医学部の一般選抜において求められる得点ラインや、英語・数学・理科の出題傾向について、過去問と合格点の分析をもとに詳しく解説します。
担当するのは、当塾講師として受験指導に携わる現役の獣医学部生。
自身の体験をふまえながら、効果的な勉強法までわかりやすくお伝えします。
鹿児島大学共同獣医学科を目指す受験生は、ぜひ参考にしてください!
- 一般選抜前期(a,b)
- 共通テストのリスニングが苦手なら、パターンb
- パターンbのほうが圧倒的に倍率が高い(2025年度 a:2倍、b:21.4倍)
- 一般選抜後期
- 個別学力試験がないため、共テで相当な点数を稼ぐ必要あり
- 2024.25年度は倍率が15.16倍と非常に高め
- 2023年度~、面接は廃止
- 各科目の入試傾向と勉強法を解説しました(2021年度~)
北海道大学 獣医学部 3年生。当予備校の講師として活躍中。
前期試験で現役合格(共通テストで8割超え)を果たし、ベレクトは数学・生物・化学・英語を指導。これまでに北海道大学など、複数の獣医学部合格者を輩出しています。
自身の受験経験と豊富な指導実績をもとに、最新の入試傾向の分析や、実践的な勉強法について、当サイトのコンテンツ執筆にも携わる。
(2025年 執筆時)
2026年度 鹿児島大学共同獣医学科「一般選抜」の入試科目・必要科目おさらい
一般選抜前期(a,b)
| 内容 | |
|---|---|
| 募集人数 | a:10名 b:10名 |
| 試験内容 | ・共通テスト:6教科8科目 ・個別学力試験:3教科(数学、英語、理科から1科目) |
| 共通テストの科目 | a 920点満点 【国語】200点 【社会】100点 【数学】200点 【理科】200点 ※物理 化学 生物から1科目 【外国語】200点 【情報】20点 b 460点満点 【国語】100点 【社会】50点 【数学】100点 【理科】100点 ※物理 化学 生物から1科目 【外国語】100点 【情報】10点 |
| 個別学力試験の科目 | 3教科3科目 a600点満点 b1200点満点 【数学】a 200点 b 400点 【理科】a 200点 b 400点 【外国語】a 200点 b 400点 |
一般選抜前期日程にはパターンaとパターンbの2種類があります。パターンaは共通テスト重視、パターンbは個別学力試験重視です。
またパターンaとパターンbでは共通テストの英語のリスニング、リーディングの得点配分が異なります。配点は以下のようになります。
| リーディング | リスニング | 合計点 | |
|---|---|---|---|
| パターンa | 100点→160点 | 100点→40点 | 200点 |
| パターンb | 100点→80点 | 100点→20点 | 100点 |
共通テストのリスニングが苦手なら、、
特にパターンbは、リスニングの点数があまり点数に反映されていません。共通テストの英語試験はクセがあるので苦手とする方もいらっしゃると思います。リスニングに自信がない方やリーディングの点数に不安がある場合は、パターンbの方が失点を抑えることができます。
ただし各パターンごとの定員は決まっているので自分はどちらのパターンが適しているかは、模試の点数の傾向や本番の共通テストの点数を照らし合わせて慎重に検討しましょう。
一般選抜後期
| 内容 | |
|---|---|
| 募集人数 | 2名 |
| 試験内容 | ・共通テストのみ:6教科8科目 |
| 共通テストの科目 | 920点満点 【国語】200点 【社会】100点 【数学】200点 【理科】200点 【外国語】200点 【情報】20点 |
後期日程は、個別学力試験が課されません。
したがって共通テストで相当な点数を稼ぐ必要があるでしょう。
なお2022年度以前は面接が課されていましたが、2023年度以降から廃止されました。
【分析】合格にはどれくらいの得点が必要?
鹿児島大学が発表している、2020~2025年の合格最低点・倍率は以下の通りです。
| 年度 | 合格最低点・合格倍率 |
|---|---|
| 2025年 | 【一般前期】 a 合格者最低点:1163.2/1520 合格倍率:2倍 b 合格者最低点:1272.6/1660 合格倍率:21.4倍 【一般後期】 合格者最低点:非公表/920 合格倍率:16倍 |
| 2024年 | 【一般前期】 a 合格者最低点:1148/1500 合格倍率:1.6倍 b 合格者最低点:1232/1650 合格倍率:23.1倍 【一般後期】 合格者最低点:非公表/900 合格倍率:15.5倍 |
| 2023年 | 【一般前期】 a 合格者最低点:1122/1500 合格倍率:2.7倍 b 合格者最低点:1173/1650 合格倍率:16.6倍 【一般後期】 合格者最低点:非公表/900 合格倍率:4.3倍 |
| 2022年 | 【一般前期】 合格者最低点:1075/1500 合格倍率:3.2倍 【一般後期】 合格者最低点:非公表/1200 合格倍率:4.0倍 |
| 2021年 | 【一般前期】 合格者最低点:1177/1500 合格倍率:3.3倍 【一般後期】 合格者最低点:非公表/1200 合格倍率:3.0倍 |
| 2020 年 | 【一般前期】 合格者最低点:1132/1400 合格倍率:3.5倍 【一般後期】 合格者最低点:非公表/1000 合格倍率:2.5倍 |
倍率について
2023年以降は前期日程はパターンaとパターンbに分かれています。しかしパターンaに比べてパターンbの倍率が非常に高くなっていることがわかります。つまり個別学力試験重視の方が、共通テスト重視よりも志願者が多い傾向があります。
後期日程の倍率は例年は3、4倍前後を推移していますが、2024年度は15倍、2025年度は16倍と非常に高くなりました。
合格最低点について
合格最低点を見てみましょう。どちらのパターンでも前期日程では最低7割以上得点する必要があります。年によっては8割近くの得点が求められます。
なおパターンに分かれる前と後で、合格最低点の得点率に大きな変化はないです。後期日程は点数が公表されていません。パターンbの方がパターンaよりもはるかに倍率が高いにも関わらず、合格最低点の得点率があまり変わらないことから、パターンaの方が比較的入りやすいとも考えられます。
【教科別】合格点や過去問から入試の傾向と勉強法を解説
ここからは、各教科の出題傾向とそれに合った勉強法を解説していきます。
各教科の出題傾向は、受験人数が多い前期入試を基に分析を行いました。
数学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:小問3問(三角関数 不等式 命題と論証) 大問2:対数方程式 大問3:数列 ベクトル 確率から1問選択 |
| 2024年 | 大問1:小問3問(確率 不等式 指数対数) 大問2:三角関数 微分法 大問3:数列 ベクトル 確率分布から1問選択 |
| 2023年 | 大問1:小問3問(図形 整数 確率) 大問2:図形と方程式 大問3:数列 ベクトル 確率分布から1問選択 |
| 2022年 | 大問1:小問3問(図形 整数 確率) 大問2:対数関数 大問3:数列 ベクトル 確率分布から1問選択 |
| 2021年 | 大問1:小問3問(式の値 図形 三角関数) 大問2:微分法 大問3:数列 ベクトル 確率分布から1問選択 |
| 2020年 | 大問1:小問3問(整数 三角関数 確率) 大問2:式と証明 大問3:数列 ベクトル 確率から1問選択 |
試験時間は90分で大問は3つです。試験時間は十分あると言えるでしょう。
問題構成
例年大問1は小問集合で大問2は微分法、積分法、三角関数などの問題、大問3は選択制で数列やベクトルが出題されています。2025年度からは旧課程では試験範囲にされていた整数と確率分布がなくなりました。それに伴い大問3で「数列・ベクトル・確率分布から1つ選択」が「数列・ベクトル・確率から1つ選択」に変わりました。
難易度
計算問題が多いですが、証明や図示を求められることもあるので解答作成を丁寧に行う習慣をつけましょう。問題の難易度は標準的で教科書に即してしっかりと勉強していれば高得点が狙えます。あまり慣れない問題だとしても誘導に乗ることで答えを導けるものがほとんどです。
対策
対策としては学校や塾で一通り単元を習い終えたら青チャートレベルの問題集を繰り返し解き、典型問題の解法を完璧にしましょう。数学は思考力が必要と言われていますが、思考力をつける前にある程度基礎となる解法を頭に入れておく必要があります。典型問題に即した問題を出題することが多いので問題を見たら解法が思いつくくらいにしましょう。
数学Ⅲが試験範囲から除外されている(詳しくは後述)ことや、標準的な問題が出題されることから数学が決して得意ではない人も対策すれば合格に近づくことができるはずです。
英語
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:文法 語彙 大問4:英作文(会話文中の和文英訳) 大問5:英作文(意見論述 120語) |
| 2024年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:文法 語彙 大問4:英作文(会話文中の和文英訳) 大問5:英作文(意見論述 120語) |
| 2023年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:文法 語彙 大問4:英作文(会話文中の和文英訳) 大問5:英作文(意見論述 120語) |
| 2022年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:文法 語彙 大問4:英作文(会話文中の和文英訳) 大問5:英作文(意見論述 120語) |
| 2021年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:文法 語彙 大問4:英作文(会話文中の和文英訳) 大問5:英作文(意見論述 120語) |
| 2020年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3;文法 語彙 大問4:英作文(会話文中の和文英訳) 大問5:英作文(意見論述 120語) |
出題傾向は毎年同じで試験時間は90分で大問は5つです。
難易度
問題のレベル自体は標準的ですが、問題量が多いので手際よくこなしていくことが求められます。
問題構成
読解問題は大問2つ分ありますが、内容説明を記述で求められたり、空所補充を課されたりと読むのにも解答を記述するにも時間がかかるでしょう。2025年には共通テストのリーディングを彷彿させるようなグラフや比較の表を用いた問題も出題されました。
文法問題は比較的標準的なので素早く終わらせることが重要です。
大問4と5では英作文が課されます。大問4は会話文中の和文英訳です。日本語だけ見ていきなり英語に訳すのは危険なので、一応文章を読んで背景情報を確認しましょう。訳す文章も問題集にある硬い文章ではなく、口語なのでどのような文法を用いるべきかは練習が必要でしょう。
大問5では100から120字という長い意見英作文が求められます。
制限時間もあるので持論を書くのではなく、いかに書きやすい内容で臨むかが重要。いきなり書き始めるのはリスクがあるので、まずは下書きをして書く内容をある程度整理してから書き始めるようにすると良いです。
90分という短い制限時間ですが、見直しの時間も取れないことはありません。特に前半の読解を超えてしまえばあとは深く読み込むというよりも、要領の良さが求められるでしょう。過去問演習をたくさん行い傾向に慣れることが重要です。
理科
化学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:総合問題(結晶格子 化学反応の速さ 中和 コロイド 芳香族化合物の同定) 大問2:無機 有機 大問3:有機 大問4:有機 大問5:理論 |
| 2024年 | 大問1:総合問題(単体 脂肪族化合物 酸化数 気体の発生 呈色反応) 大問2:理論 大問3:理論 大問4:有機 大問5:有機 |
| 2023年 | 大問1:総合問題(濃度計算 セラミックス コロイド CaとAgの化合物 同素体 アルカン PET アセチレン アニリン) 大問2:理論 大問3:有機 大問4:有機 大問5:無機 理論 |
| 2022年 | 大問1:理論 大問2:理論 大問3:有機 大問4:有機 理論 大問5:無機 理論 |
| 2021年 | 大問1:理論 大問2:無機 理論 大問3:理論 大問4:有機 理論 大問5:有機 理論 |
| 2020年 | 大問1:理論 有機 大問2:理論 大問3:理論 大問4:有機 大問5:有機 理論 |
試験時間は90分で大問は5つです。
問題構成
近年は大問に加えて総合問題として1問1答形式の知識や簡単な計算を問う形式も登場しています。平易な問題が多いので確実に得点しましょう。
難易度
問題のレベルは標準的ですが、計算や記述(理由を説明するものなど)が多いので手際よくこなすようにしましょう。
出題傾向を見ると理論化学が特に重要であることが伺えます。無機化学や有機化学との融合問題など単元に縛られない横断的な理解が必要なので、理論化学で重要な法則は計算できるようにするだけでなく、その意味を理解できるようにしましょう。
対策
対策としてまずはセミナーやリードαなどの教科書傍用の問題集を繰り返し解き、基本的な問題を完璧すると良いでしょう。
ある程度基礎が固まったら、過去問や国公立大学の標準レベルの問題を制限時間以内に解けるように。教科書に加えて資料集などを活用すると教科書には載っていない豆知識や日常での応用例などを知ることができ、知識定着の助けになります。
物理
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:力学 大問2:熱力学 大問3:電磁気 大問4:原子 |
| 2024年 | 大問1:力学 大問2:熱力学 大問3:波動 大問4:電磁気 |
| 2023年 | 大問1:力学 大問2:熱力学 大問3:波動 大問4:電磁気 |
| 2022年 | 大問1:力学 大問2:熱力学 大問3:波動 大問4:電磁気 |
| 2021年 | 大問1:力学 大問2:熱力学 大問3:波動 大問4:電磁気 |
| 2020年 | 大問1:力学 大問2:熱力学 大問3:波動 大問4:電磁気 |
出題傾向は毎年同じで試験時間は90分で大問は4つです。
問題構成
大問が4つあるので力学、熱力学、電磁気、波動の4つ満遍なく毎年出題されてきましたが2025年にはついに原子が出題されました。共通テストで勉強を辞めないようにしましょう。
また鹿児島大学は入試問題過去問題活用宣言をしており2025年度の大問2はかつて平成25年度に鹿児島大学で出題されたものを一部改変したものでした。とはいえそこまで昔の問題を遡って演習するのは現実的ではないので参考程度にするのをお勧めします。
難易度
問題の難易度は標準的と言われています。描図や導出を求められることが多いので、普段から手を動かす練習をしましょう。例えば物理を勉強するにあたり単位系を意識することはとても重要です。
対策
対策としてまずはセミナーやリードαなど教科書傍用の参考書を繰り返し解き解法を定着させましょう。ある程度基礎が固まったら重要問題集のA問題など標準レベルの入試問題に多く当たり問題数をこなしましょう。
生物
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:ホルモン 褐色脂肪組織 大問2:減数分裂 キメラ 大問3:生命の起源 進化 大問4:栄養の吸収 生態系におけるエネルギーの流れ |
| 2024年 | 大問1:遺伝情報 大問2:生殖 発生 大問3:進化 系統 生態系 大問4:生態系 食物連鎖 |
| 2023年 | 大問1:生殖 発生 体内環境 大問2:植物の反応 大問3:体内環境 大問4:代謝 |
| 2022年 | 大問1:代謝 大問2:遺伝情報 大問3:植物の反応 発生 生殖 大問4:進化と系統 生態系 |
| 2021年 | 大問1:体内環境 大問2:遺伝情報 代謝 大問3:総合問題(発生 系統 受容器 脳) 大問4:総合問題(進化 遷移 顕微鏡 生活環 生態系) |
| 2020年 | 大問1:遺伝情報 代謝 大問2:総合問題(細胞 神経 生殖 発生) 大問3:体内環境 生殖 発生 大問4:生態系 |
試験時間は90分で大問は4つです。
問題構成
2024年、2025年と2年連続して生態系におけるエネルギーの流れが出題されるなど、出題される頻度が高い分野もあります。特に2025年は褐色脂肪組織やキメラなど高校生物の知識を応用して考える興味深いテーマがありました。
難易度
問題の難易度には若干の変動があり2022年や2023年は思考力が試される問題が出題されましたが、2024年には平易な問題が多いなど傾向がつかみにくいので標準的な対策だけでは不十分なこともあり得ます。
また大問ごとに分量や難易度が異なるので時間がかかりそうな問題を後回しにして、先に解けそうな問題をやってしまうなど適宜柔軟に対応しましょう。
対策
対策としてまずは教科書や資料集の内容を完璧にしましょう。教科書を読むだけでは知識の定着に不安がある場合はセミナーやリードαなどの参考書を使用しながら読み進めるのもおすすめです。ある程度基礎が頭に入ったら入試問題にチャレンジするようにしましょう。
実験や背景知識を沢山持っていると問題を解くときに有利にはたらきます。もちろん問題に説明や誘導が付いていることもあるのですが、背景知識を持っていれば問題内容を理解するのが早くなります(思い込みは厳禁ですが、、)。
入試問題に多く当たっておくことで解けても解けなくてもこのような実験がある、このような現象があるということを知ることができるます。重要問題集や良問問題集などを活用して積極的に演習を行いましょう。
外部英語試験検定スコアについて
鹿児島大学は、外部英語試験の検定スコアを共通テストのリーディングとリスニングとして利用することができます。
対象となる試験は以下にまとめた通りです。
| 検定試験名 | スコア基準(2022∼2024年度実施分) |
|---|---|
| ケンブリッジ英検 | FCE以上 |
| 実用英語技能検定(S-CBTも含む) | 準1級合格以上(英検CBT S-CBTも含む) |
| GTEC(CBTタイプ) | 1250点以上 |
| IELTS(アカデミックモジュール) | 5.5以上(Overall Band Score) |
| TEAP(PBT版) | 334点以上 |
| TOETL iBT | 72点以上 |
| TOEIC L&R/TOEIC S&W (公開テスト) | 1095点以上(L&R785点以上かつS&W310点以上) |
以上のスコアを取得している場合、リーディングとリスニングの点数を以下のように扱うとされています。
| リーディングまたはリスニングの得点 | 得点調整後の点数 |
|---|---|
| 80点以上 | 得点を満点とみなす(みなし満点制度) |
| 80点未満 | 得点の25%を加点する(加点制度) |
共通テストで英語を受験することは必須ですが、共通テストでは高得点が取りにくいけど英検準1級なら取れそうなど、比較的自分の得意な形式の試験で勝負することができます。
高3になると忙しいので外部英語試験を受ける時間的余裕があるかわかりませんが、高2のうちに取得しておくとかなり便利な制度と言えるでしょう。
まとめ
今回は鹿児島大学の獣医学科について傾向と対策についてご紹介しました。
鹿児島大学は、英語の外部試験を導入したり、前期日程でパターンを2つ(a、b)設けたりと国立大学ながら入試にバリエーションを持たせているのが特徴です。
自分が得意とする分野や形式で受けられるメリットがある反面、選択によっては倍率や難易度に差が生じてしまう可能性もあるのでどの方法を利用するのかはよく検討するようにしましょう。
-3.png)