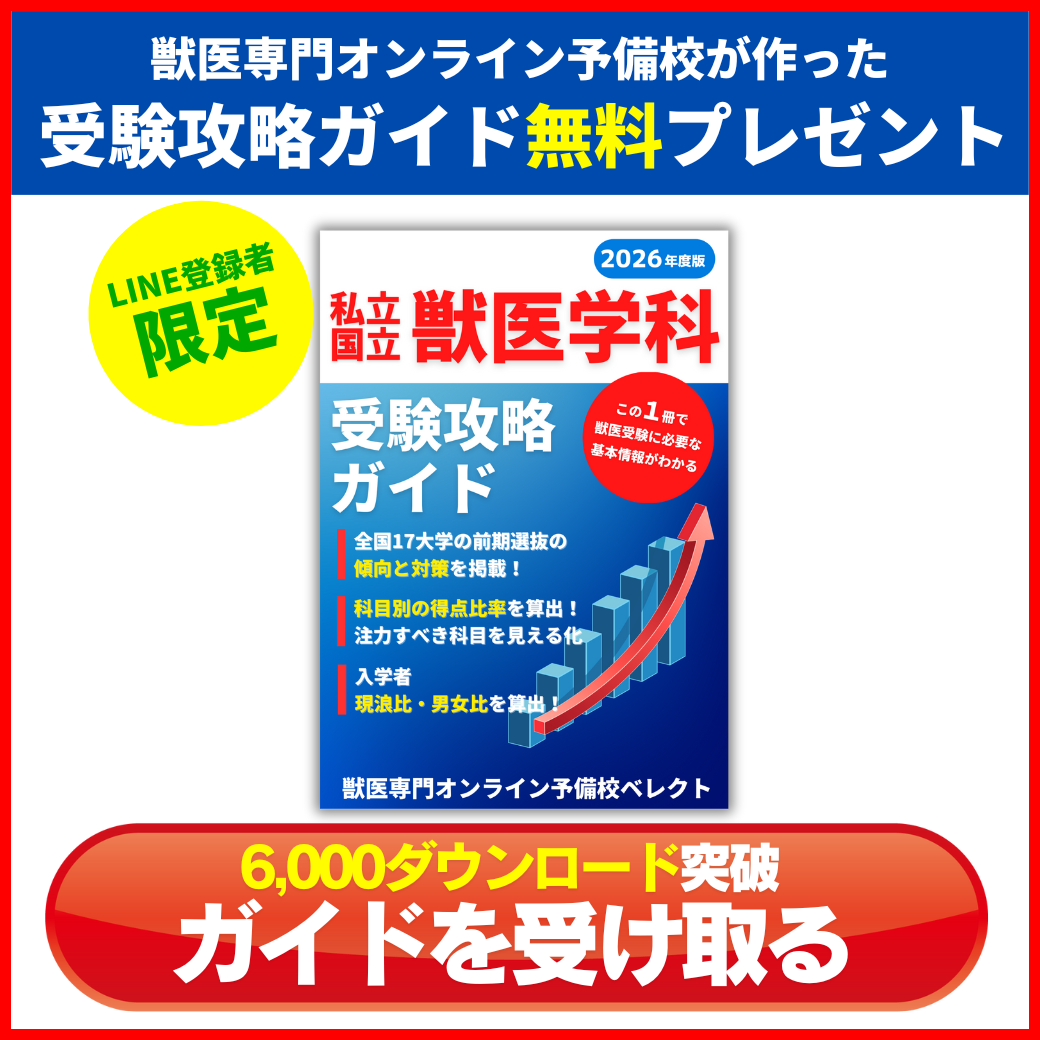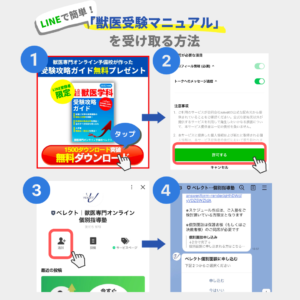こんにちは!獣医専門オンライン予備校のベレクトです。
2026年度・酪農学園大学獣医学類の一般選抜に向けて、合格点の目安や教科ごとの傾向が気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では酪農学園大学獣医学類の一般選抜において求められる得点ラインや、英語・数学・理科の出題傾向について、過去問と合格点の分析をもとに詳しく解説します。
担当するのは、当塾講師として受験指導に携わる現役の獣医学部生。
自身の体験をふまえながら、効果的な勉強法までわかりやすくお伝えします。
酪農学園大学獣医学類を目指す受験生は、ぜひ参考にしてください!
- 酪農学園大学独自の試験のみの入試は厳しめ
- 共通テスト併願は日程選びが重要
- 共通テスト利用ではほぼ入学者おらず
- 各科目の入試傾向と勉強法を解説しました(2021年度~)
北海道大学 獣医学部 3年生。当予備校の講師として活躍中。
前期試験で現役合格(共通テストで8割超え)を果たし、ベレクトは数学・生物・化学・英語を指導。これまでに北海道大学など、複数の獣医学部合格者を輩出しています。
自身の受験経験と豊富な指導実績をもとに、最新の入試傾向の分析や、実践的な勉強法について、当サイトのコンテンツ執筆にも携わる。
(2025年 執筆時)
2026年度 酪農学園大学獣医学類「一般選抜」入試の全体像
酪農学園大学獣医学類の一般選抜には第1期学力入試、併用型入試、共通テスト利用入試があります。
なお第1期学力入試と併用型入試の理科の問題は同じとなります。
2026年度【方式別】一般選抜の定員・入試科目・配点おさらい
第1期学力入試
| 募集人数 | 個別学力検査 |
|---|---|
| 42名 | 300点満点 3教科3科目 |
2025年度から酪農学園の独自の問題だけで合否を決める学力入試が獣医学類においても実施されるようになりました。
学力入試では英語、数学、それと理科1科目において個別学力検査が実施されます。
併用型入試
| 日程 | 募集人数 | 学力検査 |
|---|---|---|
| 第1期A日程(通常) | 25名 | 300点満点 【共通テスト】 数学・英語(200点満点) 【個別学力検査】 理科(100点満点) |
| 第1期A日程(理科重点) | 5名 | 400点満点 【共通テスト】 数学・英語(200点満点) 【個別学力検査】 理科(200点満点) |
| 第2期 | 5名 | 400点満点 【共通テスト】 数学・英語(200点満点) 【個別学力検査】 理科(200点満点) |
併用型入試は3種類あり共通テストと個別学力検査の両方で合格を決めます。
共通テストの英語はリーディングとリスニングのどちらも1:1で換算されます。
リスニングはリーディングより比率が低くされることが多いですが、酪農学園は違うのでしっかり点数を取っておきましょう。
個別学力検査で課される理科は化学と生物のどちらかを選択します。物理は使えないので注意しましょう。
共通テスト利用入試
| 募集人数 | 共通テスト | |
|---|---|---|
| 3教科5科目 | 5名 | 600点満点 英語・数学・理科2科目 |
| 5教科5科目 | 3名 | 600点満点 英語(リスニングも) 国語(近代以降の文章のみ) 数学 理科1科目 地歴情報(1つ選択) |
共通テスト利用入試は3教科5科目と5教科5科目方式の2つがあります。
共通テストの理科は化学と生物のほか物理も選択することができます。
なお5教科5科目方式の数学は必ずしも数学ⅠAとⅡBCの両方を受験する必要はなく、数学Ⅰ、数学ⅠA、数学Ⅱ、数学ⅡBCのいずれか1科目で受験できます。
【傾向分析】方式ごとの合格ライン|合格にはどれくらいの得点が必要?
| 年度 | 合格倍率(受験者/合格者) 合格平均点 |
|---|---|
| 2025年 | ・第1期学力入試:6.2倍(231.1/300) ・併用型入試 L第1期A日程(通常):3.4倍(228.9/300) L第1期A日程(理科重点):3.6倍(306.3/400) L第2期:24.8倍(343.1/400) ・共通テスト利用入試 L3教科5科目:10.3倍(511.1/600) L5教科5科目:4.6倍(504.8/600) |
| 2024年 | ・併用型入試 L第1期A日程(通常):3.0倍(210.7/300) L第1期A日程(理科重点):2.9倍(278.8/400) L第2期:20.3倍(327.8/400) ・共通テスト利用入試 L3教科5科目:21.9倍(506.2/600) L5教科5科目:24.0倍(509.3/600) |
| 2023年 | ・併用型入試 L第1期A日程(通常):3.0倍(217.1/300) L第1期A日程(理科重点):2.9倍(284.3/400) L第2期:20.3倍(340.1/400) ・共通テスト利用入試 L3教科5科目:21.9倍(516.8/600) L5教科5科目:24.0倍(508.2/600) |
| 2022年 | ・併用型入試 L第1期A日程(通常):3.3倍(不明) L第1期A日程(理科重点):3.3倍(不明) L第2期:5.6倍(不明) ・共通テスト利用入試 L3教科5科目:42.2倍(不明) L5教科5科目:31.8倍(不明) |
※平均点は2025年度のみ第1志望合格者のデータ
第1期学力入試は少し厳しめ
2025年度から新たに始まった第1期学力入試ですが、初年度は倍率は6倍を超え、合格平均点も7割強(ほぼ8割)という結果になりました。
やはり共通テストが合否に関与しない点で共通テストの出来に関わらず多くの受験生が受験したと思われます。
併用型入試はA日程がねらい目
併用型入試第1期A日程は通常型も理科重点型も平均点、倍率ともに差はないです。
平均点は7割、2025年度は公開されていませんが合格最低点は6割ほどです。
倍率も3倍前後なので獣医学部受験の中では低い部類に入るでしょう。
対して第2期は定員が少なく倍率が高いことに加え、平均点も8割を超えているためなかなかハイレベルな戦いです。
なお併用型入試第1期は第1期学力入試の導入で定員が減少しても合格平均点や倍率に大きな差は生じませんでした。
共通テスト利用入試は結局ほぼ入学しない
共通テスト利用入試はどちらの方式を選択しても倍率が20倍を超え、平均点も8割を超えています。
2025年度は公表されていませんが合格最低点も8割を超えているので得点率を見ると国公立大学レベルです。
しかし大学が公表している入試データによると、共通テスト利用入試で高い倍率を突破した合格者がほぼ入学していないことが分かります。
共通テスト利用入試は試験会場に行く必要がなく、併願校として出願する人が多いため必然的にレベルが高くなります。
したがって酪農学園大学を専願する受験生にとってはライバルが多くこの入試方式で合格を検討するのは控えた方が良いでしょう。
【教科別】過去問から入試の傾向と勉強法を解説
先述した通り第1期学力入試の理科と併用型入試の理科の試験問題は同じです。
英語と数学はかつて実施していた酪農学園大学の独自の試験の過去問と2025年度の問題掲載しました。
英語
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:長文 ※詳細は非公開 大問2:長文 ※詳細は非公開 大問3:文法問題(文中に当てはまる適切な語句を選択) 大問4:文法問題(和文を元に語句を並び替える) |
| 2020年 | 大問1:長文(文中に当てはまる適切な語句を選択 10問) 大問2:長文(内容説明 正誤問題 本文読み取り) 大問3:文法問題(文中に当てはまる適切な語句を選択) 大問4:文法問題(和文を元に語句を並び替える) |
| 2019年 | 大問1:長文(本文読み取り 内容説明 要約文完成) 大問2:長文(内容説明 本文読み取り) 大問3:文法問題(文中に当てはまる適切な語句を選択) 大問4:文法問題(和文を元に語句を並び替える) |
| 2018年 | 大問1:長文(内容説明 本文読み取り 要約文完成) 大問2:長文(内容説明 本文読み取り) ※問題文は非公開 大問3:文法問題(文中に当てはまる適切な語句を選択) 大問4:文法問題(和文英訳) |
問題傾向
英語の試験問題は60分、大問は4つです。
大問のうち2つは長文問題で残りの2つは文法問題です。
生憎2025年度の問題が非公開となっていますが、過去に実施した試験問題を見ると長文問題はすべて記号選択式であり、本文の読み取りと内容説明を問う点で共通テストにかなり似ています。
文法問題は基本的に文法的に適切な語句を選択する形式と、日本語訳をもとに語句を適切な順番に並び替える形式で出願されています。
難易度
長文はかなり長めの文章が課されものによっては専門性が高く、注釈が多いものもある(獣医学に関するものも出題されています)ので素早く処理しないと時間が足りなくなります。
文法問題は教科書は参考書レベルで平易です。
対策
長文対策は基本的に共通テストの英語の対策と同じで長めの文章の内容を読み取り一発で設問に解答する練習を積みましょう。
文法問題は教科書は参考書(ビンテージやネクストステージなど)を用いて英文法を例文付きで覚えるようにすると正しい選択肢が眼に留まりやすくなります。
数学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:小問集合(展開式 三角関数 場合の数 対数 積分 数列) 大問2-1:確率変数 2-2:ベクトル ※どちらかを選択 大問3:積分 |
| 2020年 | 大問1:小問集合(解と係数の関係 場合の数 対数方程式 積分 ベクトル) 大問2:領域 大問3:三角関数 |
| 2019年 | 大問1:小問集合(不等式 剰余の定理 三角関数 対数関数 極大値 集合と命題) 大問2:数列 大問3:ベクトル |
| 2018年 | 大問1:小問集合(虚数 確率 対数不等式 ベクトル 積分の定義 積分) 大問2:三角関数と座標平面 大問3:数列 |
問題傾向
数学の試験時間は60分、大問は3つです。2025年度は大問2が選択制になっていました。
大問1は小問集合で各分野から満遍なく出題されている印象です。
簡単な問題なので手堅く得点したいところです。
なお大問1、2は計算過程を記述しますが、大問3は共通テストのように穴埋め式になっており答えだけ解答するようになっています。
難易度
問題の難易度は比較的平易で教科書の章末問題レベルがすらすら解ければ大問1,2は取れるでしょう。
大問3は見慣れない形式で出題されますが、共通テストと同様誘導がついているので誘導に乗っていけば答えにたどり着くことができます。
対策
まずは教科書の練習問題、章末問題や教科書傍用参考書(4STEPなど)を何度もこなし基本的な解法を身につけましょう。
あらかた身についてきたら過去問や傾向が似ている入試問題を時初見の問題にも対処できるようにします。
誘導に乗って解く練習は共通テストと似ているので活用すると良いです。
理科
化学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:理論化学(気体) 大問2:無機化学(物質の同定) 大問3:理論化学(二段階電離 電離定数) 大問4:有機化学(構造決定) |
| 2024年 | 大問1:理論化学(電離定数) 大問2:理論化学(コロイド) 大問3:無機化学 理論化学(金属の反応 気体の発生) 大問4:有機化学(有機化学化合物の抽出 分離) |
| 2023年 | 大問1:理論化学(分子間の結合) 大問2:無機化学(ヨウ素滴定法) 大問3:理論化学 無機化学(気体) 大問4:有機化学(セッケン ヨウ素価 けん化価) |
| 2022年 | 大問1:理論化学(気体 溶解度) 大問2:理論化学(酸化還元 酸化還元滴定) 大問3:無機化学 理論化学(金属イオンの同定 溶解度積) 大問4:有機化学(エステル化 セッケン 油脂) |
問題傾向
化学の試験時間は60分、大問は4つです。
理論化学のウエイトが大きいので計算モノを苦手にしないようにしましょう。
難易度
典型的な問題ではなく、ヨウ素滴定や二段階電離、けん化価など、マイナーな範囲がテーマになっていることが多いので初見に弱い受験生にとってはとっつきにくいかもしれません。
対策
まずは教科書や資料集に書いてある事柄を把握しましょう。太字だけ覚えるのでは不十分です。
リードαやセミナーなどで典型的な計算練習を積んだ上で過去問演習を行うと効率的です。
また全体的に計算が多いので、理論化学に限らず無機化学や有機化学でも計算に慣れておくとハードルが下がるでしょう。
生物
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:プラスミド 大問2:生命の起源 進化 大問3:生態系 大問4:脳 視覚 大問5:ホルモン |
| 2024年 | 大問1:転写 翻訳 PCR法 大問2:生態系 大問3:光合成 大問4:植物の受粉 ホメオティック遺伝子 大問5:動物の系統樹 |
| 2023年 | 大問1:胚の発生 大問2:酵素反応 大問3:窒素同化 大問4:社会性昆虫 血縁度 大問5:動物の行動 |
| 2022年 | 大問1:酸素解離曲線 胎児循環 大問2:眼の発生 視覚 大問3:進化 分子系統樹 大問4:減数分裂 検定交雑 大問5:細胞小器官 |
問題傾向
生物の試験時間は60分、大問は5つです。
満遍なく出題されていますが、その中でも生態系と進化は頻出なのでしっかり読んでおきましょう。
また記号選択や語句記述の他に40字程度から長いと150字ほどの論述問題が出題されています。
難易度
かなり細かい用語(教科書に忠実に)が問われており、論述問題も多いので制限時間を鑑みると問題のレベルは決して易しくはないです。
対策
対策としてまずはセミナーやリードαを解きつつ教科書や参考書を読み知識を定着させましょう。
共通テストでは単語単体を問われることはなくなりましたが、個別学力検査では記述させられるので手を動かして勉強しましょう。
論述問題はただ文字数を揃えるのではなく、要点を押さえて書くように意識しましょう。
場合によっては学校や予備校、塾の先生に添削してもらいましょう。
共通テスト利用方式の特徴と戦略
先述した通り共通テスト利用入試は倍率が高く、合格最低点も高いわりに合格者がほぼ入学していないのが事実です。
したがって酪農学園大学を専願する場合は共通テスト利用入試ではなく併用型入試、あるいは第1期学力入試を受験するのが得策でしょう。
【まとめ】酪農学園大学獣医学類で合格を勝ち取るためのポイント
酪農学園大学は入試方式が変わったばかりなので2026年度の受験生の動向が掴みにくいところもありますが、勉強方法に関しては従来と変わらずに対応できます。
大学のホームページにも以前実施していた数学と英語の独自の試験問題が掲載されているので、それらを上図に活用しつつ演習を重ねましょう。
また入試方式によって倍率や平均点が異なるため併願で受けるのか、専願で受けるのかで出願する方式を検討すると勉強時間を集約させることができます。
-3.png)