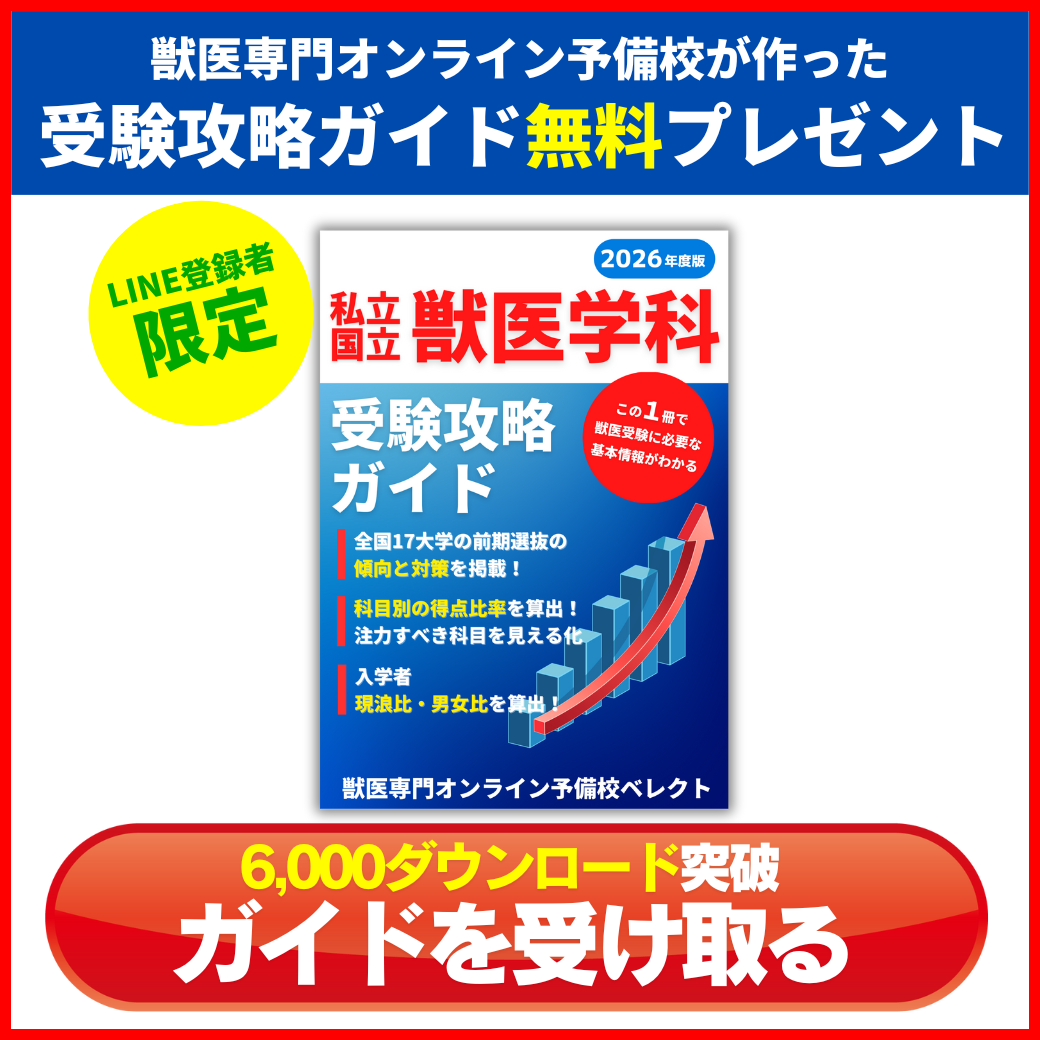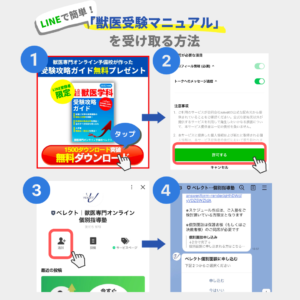こんにちは!獣医専門オンライン予備校のベレクトです。
2026年度・麻布大学獣医学科の一般選抜に向けて、合格点の目安や教科ごとの傾向が気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では麻布大学獣医学科の一般選抜において求められる得点ラインや、英語・数学・理科の出題傾向について、過去問と合格点の分析をもとに詳しく解説します。
担当するのは、当塾講師として受験指導に携わる現役の獣医学部生。
自身の体験をふまえながら、効果的な勉強法までわかりやすくお伝えします。
麻布大学獣医学科を目指す受験生は、ぜひ参考にしてください!
- Ⅰ期のB日程を受験しよう
- 全科目選択式なので記述がいらない
- 理科は文量に注意
- 各科目の入試傾向と勉強法を解説しました(2021年度~)
北海道大学 獣医学部 3年生。当予備校の講師として活躍中。
前期試験で現役合格(共通テストで8割超え)を果たし、ベレクトは数学・生物・化学・英語を指導。これまでに北海道大学など、複数の獣医学部合格者を輩出しています。
自身の受験経験と豊富な指導実績をもとに、最新の入試傾向の分析や、実践的な勉強法について、当サイトのコンテンツ執筆にも携わる。
(2025年 執筆時)
2026年度 麻布大学獣医学科「一般選抜」入試の全体像
麻布大学獣医学科の一般選抜には、一般入学試験と大学入学共通テスト利用試験があります。
2026年度【方式別】一般選抜の定員・入試科目・配点おさらい
一般入学試験
| 日程 | 募集人数 | 内容 |
|---|---|---|
| Ⅰ期B日程 | 67名 | 3教科3科目(300点満点) |
| Ⅰ期D日程 | 5名 | 3科目3科目(300点満点) |
| Ⅱ期 | 5名 | 3教科3科目(300点満点) |
一般入学試験はⅠ期とⅡ期で計3回実施され、出題科目や配点は3回とも同じです。
理科は、物理がなく化学と生物のみであるため注意しましょう。
大学入学共通テスト利用入学試験
| 日程 | 募集人数 | 内容 |
|---|---|---|
| Ⅰ期 | 7名 | 3教科3科目(600点満点) |
| Ⅱ期 | 5名 | 3教科3科目3科目(600点満点) |
大学入学共通テスト利用入学試験はⅠ期とⅡ期に分かれますが、合否の判定方法はどちらも同じです。
なお麻布大学は英語200点満点のうちリーディングを160点満点、リスニングを40点満点に換算するためリーディングを得意にしておくと有利になるでしょう。
理科は物理、化学、生物から1科目を選択しますが「基礎あり」でも受験することができます。
理系の受験生の多くは受験しないと思いますが、物理基礎・化学基礎・生物基礎から2科目を選択し素点×2で換算することもできます。
【傾向分析】方式ごとの合格ライン|合格にはどれくらいの得点が必要?
年によって若干入試の区分が異なります。
| 年度 | 合格倍率(受験者/合格者)・合格最低点 |
|---|---|
| 2025年 | ・一般入学試験 LⅠ期B:10.3倍(226/300) LⅠ期E:35.2倍(283/300) LⅡ期:103.7倍(非公表) ・共通テスト利用 LⅠ期:5.8倍(480/600) LⅡ期:7.0倍(非公表) |
| 2024年 | ・一般入学試験 LⅠ期B:9.1倍(215/300) LⅠ期F:24.8倍(267/300) LⅡ期:124.0倍(非公表) ・共通テスト利用 LⅠ期:6.3倍(466/600) LⅡ期:6.7倍(494.6/600) |
| 2023年 | ・一般入学試験 LⅠ期A:11.3倍(264/300) LⅠ期F:5.5倍(191/300) LⅡ期:26.9倍(213/300) ※共通テスト利用は不明 |
| 2022年 | ・一般入学試験 LⅠ期:4.9倍(190/300) LⅡ期:26.3倍(221/300) ・共通テスト利用 LⅠ期:4.8倍(420/600) LⅡ期:3.1倍(415/600) |
| 2021年 | ・一般入学試験 LⅠ期:5.0倍(211/300) LⅡ期:21.3倍(205/300) ・共通テスト利用 LⅠ期:5.2倍(500/600) LⅡ期:3.0倍(501/600) |
Ⅰ期はB日程
一般入学試験はⅠ期のB日程が倍率、合格最低点ともに合格しやすいと言えるでしょう。
とはいえ倍率は10倍超え、合格最低点も7割超えであるため確実に合格するには8割超えの得点を狙いましょう。
Ⅰ期の2回目の日程は、定員が少ない上に、合格最低点すら8割以上であるため合格するのは難しいです。
例えば2025年のⅠ期E日程は300点満点中最低点が283点、平均点が288点、最高点が297点と1点を争う戦いになりました。
Ⅱ期は事実上不可能
一般入学試験のⅡ期は近年倍率が100倍を超えており、合格するのは事実上不可能に近いです。
2023年までは定員(10名)に対し12名ほどの合格者を出していましたが、2024年度は2名、2025年度は3名しか合格者を出していません。
合格者が募集人数以下になるケースもあることを覚えておきましょう。
共通テスト利用の合格最低点は変動が大きい
共通テスト利用入試は、例年Ⅰ期もⅡ期も倍率や合格最低点に大きな差が見られないです。
とはいえ合格最低点は年によって変動が大きく、7割を切っている年もあれば8割を超えた年もあります。
とりあえず、8割以上の得点があれば安心でしょう。
Ⅰ期B日程【教科別】合格点や過去問から入試の傾向と勉強法を解説
募集定員がもっとも多い、Ⅰ期B日程について解説します。
英語
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:長文(穴埋め 意味説明 内容真偽) 大問2:長文(穴埋め 意味説明 内容説明) 大問3:文法問題(穴埋め) |
| 2024年 | 大問1:長文(穴埋め 意味説明 内容真偽) 大問2:長文(穴埋め 意味説明 内容説明) 大問3:文法問題(穴埋め) |
| 2023年 | 大問1:長文(穴埋め 意味説明 内容真偽) 大問2:長文(穴埋め 意味説明 内容説明) 大問3:文法問題(穴埋め) |
| 2022年 | 大問1:長文(穴埋め 意味説明 内容真偽) 大問2:長文(穴埋め 意味説明 内容説明) 大問3:文法問題(穴埋め) |
問題傾向
試験時間は60分、大問は3つです。
長文2つは穴埋めなどがあるもののすべて選択式なので、英作文や和訳の記述を課されることはありません。
文法問題も同様に全て選択式です。
全体的にかつてのセンター試験と似ています。
難易度
長文がそこまで長くないので、時間がギリギリになることはなさそうです。
難易度は標準的でしょう。
文法の穴埋め問題は問題文の言っている内容が掴めれば適切な選択肢を選べるでしょう。
対策
問題を早く解いて、見直しの時間を増やした方が高得点が期待できます。
教科書の長文が読めるようになったら、初見の問題をどんどん練習しましょう。
長文問題でなかなかスピードが出ない場合は、自分が認識するのが遅い英文法のパターンを見つけて意識すると効果的です。
英文法は一通り内容を入れたらNextStageやVintageなど、問題数の多い参考書を何周もし、可能ならば例文ごと暗記してしまいましょう。
そこまでは覚えられないとよく思われがちですが、文章として覚えることで初見であっても「この流れ、見たことあるぞ」と気が付きやすくなります。
数学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:小問集合(二項定理 三角関数 虚数 ベクトル) 大問2:図形と方程式 積分 大問3:数列 大問4:積分 微分 |
| 2024年 | 大問1:小問集合(因数分解 整数 剰余の定理 三角関数 対数方程式 確率 集合と命題) 大問2:三角関数 大問3:数列 大問4:微分 積分 |
| 2023年 | 大問1:小問集合(対数計算 整数 三角関数 場合の数 対数方程式) 大問2:三角関数 微分 大問3:数列 大問4:積分 |
| 2022年 | 大問1:小問集合(n進法 集合と命題 ベクトル 確率 データの分析 関係式を満たす多項式) 大問2:図形と方程式 領域 大問3:数列 大問4:積分 微分 |
問題構成
試験時間は60分、大問は4つです。
大問1は例年小問集合で幅広く、満遍なく出題されます。
また数列はほぼ毎年出題されているので必ずマスターしておきましょう。
数列の他には、積分やそれを微分して最大値を求める問題、三角関数が出題される傾向が高いです。
記述式ではなく、穴埋め式(共通テストみたいな)なので答えさえ合っていればOKです。
難易度
問題の難易度は標準的です。
とはいえ小問集合など計算が多いので、計算ミスをして失点することがないようにしましょう。
また二項定理やn進法などの計算は、一般的な二次試験の数学では出題されないので、手薄になっている受験生も多いと思います。
共通テストが終わったからと忘れないようにしましょう。
対策
教科書の章末問題や教科書傍用参考書、網羅系参考書(青チャートなど)をまずは完璧にし、それからはセンター試験過去問や標準的な難易度はの入試問題集を解きましょう。
穴埋め形式とはいえ、センター試験や共通テストほど誘導がしっかりしているわけではないので、センター試験や共通テストが解けるだけでは不十分です。
解法をしっかりと自分の中で組み立てられるようにしましょう。
理科
化学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:小問集合 大問2:理論化学(pH計算 溶解度) 大問3:理論化学(結晶格子 気体) 大問4:理論化学(燃料電池) 大問5:理論化学(エンタルピー) 大問6:理論化学(反応速度定数) 大問7:理論化学(溶解度積) 大問8:無機化学(化合物の性質 工業的製法) 大問9:無機化学(金属イオンの分離操作) 大問10:有機化学(異性体 物質同定) 大問11:有機化学(芳香族化合物の分離) 大問12:有機化学(タンパク質含有率 重合度) |
| 2024年 | 大問1:小問集合 大問2:理論化学(物質の純度 溶解度曲線 酸化還元) 大問3:理論化学(分子間力 凝固点) 大問4:理論化学(平衡) 大問5:理論化学(溶解熱) 大問6:理論化学(鉛蓄電池) 大問7:理論化学(ハーバー・ボッシュ法) 大問8:理論化学(速度定数) 大問9:無機化学(複塩) 大問10:理論化学 無機化学(沈殿) 大問11:有機化学(異性体 アルコールの酸化) 大問12:有機化学(けん化価 ヨウ素価) 大問13:有機化学(ビニロン) |
| 2023年 | 大問1:小問集合 大問2:理論化学(分子の形 電子対) 大問3:理論化学(気体の発生) 大問4:理論化学(浸透圧) 大問5:理論化学(結晶格子) 大問6:理論化学(電気分解) 大問7:理論化学(燃焼熱) 大問8:理論化学(圧平衡定数) 大問9:理論化学(緩衝液) 大問10:無機化学(金属の性質) 大問11:無機化学(金属イオンの分離) 大問12:有機化学(シストランス異性体 オゾン分解) 大問13:有機化学(芳香族化合物 官能基) 大問14:有機化学(高分子化合物 重合度) |
| 2022年 | 大問1:小問集合 大問2:理論化学(水溶液 コロイド) 大問3:理論化学(水銀だめ 飽和蒸気圧) 大問4:理論化学(ヘンリーの法則) 大問5:理論化学(凝固点降下) 大問6:理論化学(電気分解) 大問7:理論化学(速度定数) 大問8:理論化学(緩衝液) 大問9:無機化学(金属の性質 炎色反応 沈殿の色) 大問10:有機化学(構造決定) 大問11:有機化学(芳香族化合物 構造決定) 大問12:有機化学(合成高分子化合物) 大問13:有機化学(高分子化合物 重合度) |
問題構成
麻布大学の化学は、非常に問題数が多く年によりますが大問が13問程度です。
記述式ではなく全て選択式です。
試験時間は60分なのでかなり厳しいですが、大問によっては知識系で一瞬に終わってしまうものもあります。
また理論化学の計算問題が幅広く出題されます。
緩衝液や平衡、電気分解など普通の二次試験ではその中から、抜粋して大問が組まれるところが、麻布大学では全て出題されると言っても過言ではありません。
そのため苦手分野があるとあっという間に失点してしまいます。
難易度
問題の難易度は基本的には標準的ですが、計算方法が思いつかなかったり、見慣れない実験が出てくると時間が足りなくなるかもしれません。
対策
まずは公式を完璧にして、セミナーやリードαなど教科書傍用参考書で基本的な計算問題パターンを暗記しましょう。
麻布大学の化学で出題されるような計算問題は、重要問題集などでは載っていないことが多いです。
共通テストやセンター試験のような「短い問題が大量にある」問題を解くようにしましょう。
共通テストに似ているとはいえ数学と同様にそこまで誘導がしっかりしておらず、かつ麻布大学の方が難しいため最終的には過去問を沢山こなして形式に慣れるしかありません。
知識だけでは高得点が取れないので、計算から逃げないようにしましょう。
生物
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:酵素 大問2:免疫 ワクチン 大問3:生態系 水質 生物濃縮 大問4:進化 大問5:呼吸の代謝経路 呼吸商 大問6:プライマー 大問7:視覚器 |
| 2024年 | 大問1:細胞周期 大問2:核酸の構造 構成 大問3:遺伝子型 大問4:体液 酸素運搬 大問5:ミツバチダンス 大問6:植物ホルモン 大問7:生態系 大問8:進化 |
| 2023年 | 大問1:光合成 大問2:遺伝子組み換え PCR法 大問3:遺伝病 伴性遺伝 大問4:体液の浸透圧調整 大問5:網膜 視細胞 大問6:植物の屈性 大問7:動物の社会性 大問8:遺伝子頻度の変化 |
| 2022年 | 大問1:細胞内小器官 大問2:遺伝子の発現 調節領域 大問3:神経胚 大問4:肝臓 体温調節 大問5:筋肉 神経の興奮 大問6:植物ホルモン 大問7:生態系 物質生産 大問8:進化 分子時計 |
問題構成
試験時間は60分、大問は7-8つです。
幅広く出題されていますが、生態系と進化は頻出です。
解答形式は記述式ではなく選択式です。
難易度
遺伝子の問題など文量が多く、化学よりも1大問あたりも小問の数が多いので時間配分が難しいです。
基礎的な知識が頭に入っていれば内容自体はそこまで難しくなく、標準的でしょう。
対策
まずは教科書やセミナー、リードαなどを繰り返し知識を完璧にします。
先述した通り生態系と進化は頻出ですが、神経や遺伝子などに比べると手薄になりがちな単元なのでキーワードを抑えつつ表やグラフの意味を理解しましょう。
記述式ではないものの、覚える際は図を写すなり自分の言葉で説明するなり手を動かしましょう。
知識が定着してきたら、過去問を使いスピード感に慣れましょう。
共通テストと形式は似ているとはいえ共通テストの方が知識が少なく考察が多めです。
知識は引き続きセミナーやリードαを繰り返し、考察問題の選択肢を選ぶ練習で共通テストを使うと良いでしょう。
共通テスト利用方式の特徴と戦略
共通テスト利用入試のⅠ期とⅡ期では差が見られないものの、合格最低点は年によって変動しています。
例年8割の得点があれば合格することができるので、ぜひ出願しましょう。
【まとめ】麻布大学獣医学科で合格を勝ち取るためのポイント
麻布大学の一般選抜は、選択式とはいえ共通テストとは違う難しさがあります。
傾向に沿った勉強をするには、1冊何かを極めるよりは形式が似たものを集めて解く方が良いでしょう。
また一般入学試験は3回あるとは言え、事実上B日程で合格するしかありません。
B日程で合格するためには、他の私立獣医の入試スケジュールの兼ね合いも重要になります。
対策する時間を十分に確保しましょう。
-3.png)