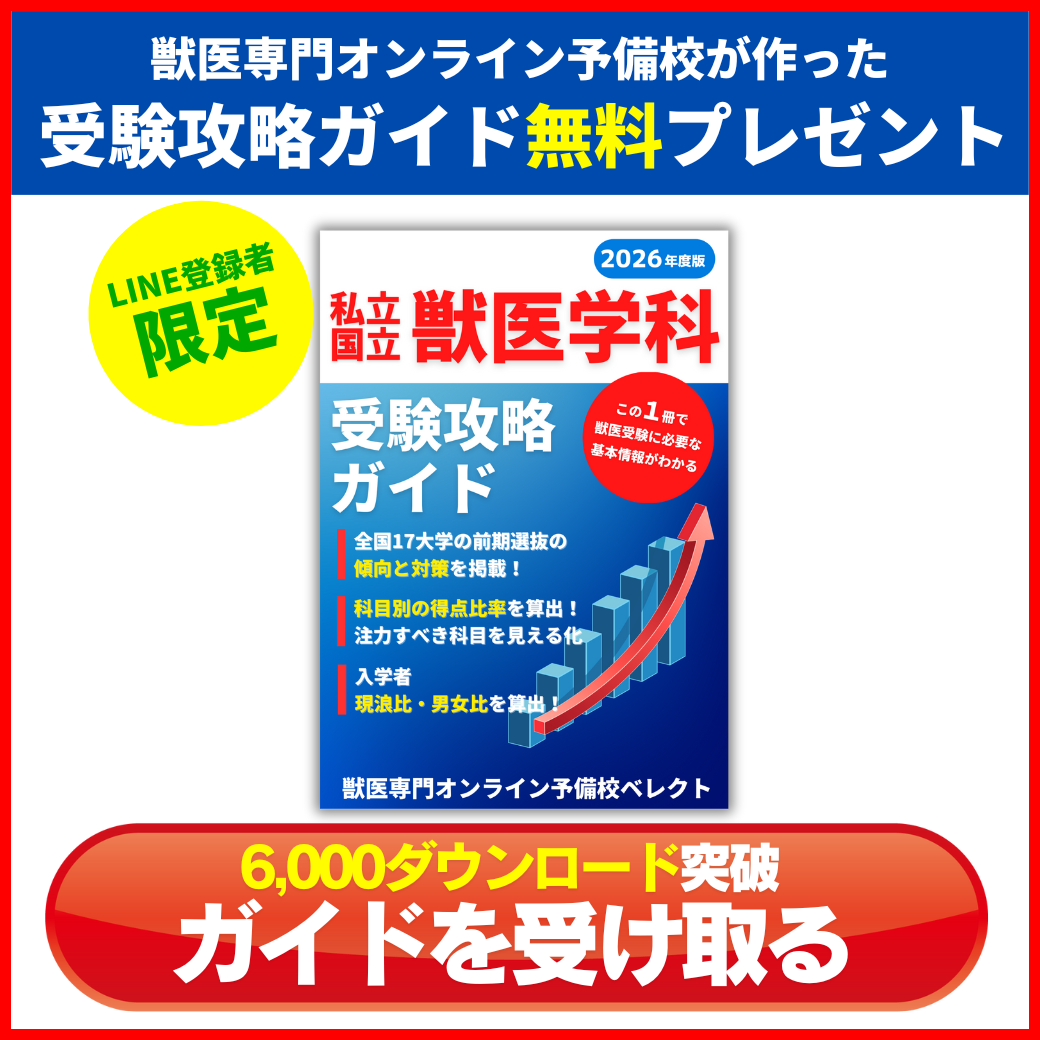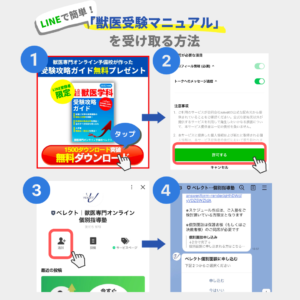こんにちは!獣医専門オンライン予備校のベレクトです。
2026年度・北里大学獣医学科の一般選抜に向けて、合格点の目安や教科ごとの傾向が気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、北里大学獣医学科の一般選抜において求められる得点ラインや、英語・数学・理科の出題傾向について、過去問と合格点の分析をもとに詳しく解説します。
担当するのは、当塾講師として受験指導に携わる現役の獣医学部生。
自身の体験をふまえながら、効果的な勉強法までわかりやすくお伝えします。
北里大学獣医学科を目指す受験生は、ぜひ参考にしてください!
- 共通テスト利用は5教科受験がねらい目
- 全体的に倍率が落ち着いていている
- 生物は考察問題が多く、やや難しめ
北海道大学獣医学部3年生。高校時代に共通テストで8割超を達成し、現役で獣医学部に合格。
現在は獣医専門オンライン予備校ベレクトで英語・理科を中心に指導し、帯広畜産大学をはじめ複数の獣医学部合格者を輩出しています。自身の受験経験と最新の入試分析をもとに、実践的な勉強法を発信中。
(2025/8月執筆時)
2026年度 北里大学大学獣医学科「一般選抜」入試の全体像
北里大学獣医学科の一般選抜には一般選抜試験(前期/後期)と共通テスト利用選抜試験(前期/後期)があります。
2026年度【方式別】一般選抜の定員・入試科目・配点おさらい
一般選抜試験
| 日程 | 募集人数 | 内容 |
|---|---|---|
| 前期 | 45名 | 3教科3科目(300点満点) |
| 後期 | 15名 | 3教科3科目(300点満点) |
一般選抜試験は前期と後期があります。
後期日程は15名と、募集人数が比較的多いです。
前期も後期も3教科3科目の300点満点です。
理科は化学、物理、生物の3科目から1科目を選択します。
共通テスト利用選抜試験
| 日程 | 募集人数 | 内容 |
|---|---|---|
| 前期(3教科) | 8名 | 3教科3科目(600点満点) ※リスニングを含む |
| 前期(5教科) | 4名 | 5教科5科目(900点満点) 【英語】200点※リスニングを含む 【数学】200点 【国語】200点※古典を含む 【地理歴史】または【公民】100点 |
| 後期 | 3名 | 3教科3科目(600点満点) ※リスニングを含む |
共通テスト利用選抜試験にも前期と後期があります。
定員は前期の方が多めですが、依然少ないです。
数学は数学ⅠAとⅡBCの素点の合計点を算出しますが、理科は1科目を選択肢、素点を2倍して換算します。
北里大学を専願する場合、理科に関しては1科目を極めると良いでしょう。
【傾向分析】方式ごとの合格ライン|合格にはどれくらいの得点が必要?
| 年度 | 合格倍率(受験者/合格者)・合格最低点 |
|---|---|
| 2025年 | ・一般 L前期:4.4倍(209点) L後期:29.9倍(233点) ・共テ利用 L前期3教科:4.8倍(464点) L前期5教科:3.3倍(683点) L後期:合格者なし ※ただしパスナビには、合格者がいないはずなのに何故か合格最低点が記載されています。パスナビ(旺文社) |
| 2024年 | ・一般 L前期:4.4倍(223点) L後期:15.9倍(234点) ・共テ利用 L前期3教科:6.3倍(469点) L前期5教科:4.1倍(689点) L後期:13倍(506点) |
| 2023年 | ・一般 L前期:4.5倍(209点) L後期:6.8倍(230点) ・共テ利用 L前期3教科:5.6倍(459点) L前期5教科:5.3倍(686点) L後期:12.7倍(538点) |
| 2022年 | ・一般 L前期:4.4倍(217点) L後期:16.8倍(251点) ・共テ利用 L3教科:5.6倍(423点) L5教科:3.9倍(637点) |
一般選抜の前期は狙い目
一般選抜の前期日程の倍率は例年5倍ほどで、合格最低点も7割程度です。
決して低い倍率ではありませんが、日本獣医生命科学大学や麻布大学、日本大学と比べると比較的落ち着いた倍率でしょう。
後期日程の倍率は他の私立獣医のように跳ね上がり、合格最低点も8割を超えているため、合格を狙うのは難しいです。
共通テスト利用は5教科の方が入りやすい
共通テスト利用の前期日程には3教科と5教科がありますが、例年5教科の方が倍率、合格最低点ともに低くなっています。
5教科で受験する場合、国語と社会も点数を揃える必要があり大変ですが、国立志望で北里は併願である場合は5教科の方で出願した方が良さそうです。
また、3教科より5教科の方が定員に対して多めに合格者が採られているのも特徴です。
【教科別】合格点や過去問から入試の傾向と勉強法を解説
募集定員がもっとも多い、前期日程について解説します。
英語
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:長文(選択穴埋め 意味選択 内容一致) 大問2:文法問題(選択穴埋め) 大問3:会話文(内容一致) 大問4:文章問題(選択穴埋め) 大問5:文法問題(選択並び替え) |
| 2024年 | 大問1:長文(選択穴埋め 意味選択 内容一致) 大問2:文法問題(選択穴埋め) 大問3:会話文(内容一致) 大問4:文章問題(選択穴埋め) 大問5:文法問題(選択並び替え) |
| 2023年 | 大問1:長文(選択穴埋め 意味選択 単語の変化形 内容一致 関連文章についての設問) 大問2:会話文(選択穴埋め 内容一致) 大問3:会話文(適切な対応文に) 大問4:会話文(選択穴埋め) |
| 2022年 | 大問1:長文(意味選択 内容一致 要約文の選択穴埋め) 大問2:文法問題(選択穴埋め) 大問3:文章問題(選択穴埋め) 大問4:文法問題(選択並び替え) 大問5:英語の説明文から該当する動物を当てる問題 |
| 2021年 | 大問1:長文(選択穴埋め 意味選択 内容一致) 大問2:会話文(意味選択 内容一致) 大問3:文法問題(選択穴埋め) 大問4:文章問題(選択穴埋め) |
問題構成
試験時間は60分、大問は4~5つです。
2023年以前はやや問題傾向が異なりますが、長文問題や会話文が頻出なことに変わりありません。
難易度
選択形式とはいえ、選択文を含めて問題の分量がかなり多いです。
60分以内に全てを解き切るためには、かなりの速読力が必要でしょう。
対策
扱われる文法や文章の内容自体は標準的であるため、基礎的な問題を素早く解く練習をしましょう。
先に選択肢に目を通してから、本文に入ると時短になります。
年によっては会話文の形式の問題が複数の大問分あることもあります。
長文問題も長文とはいえ、かなり穴だらけのケースもあります。
普段から文章のつながりや論理関係を意識しましょう。
数学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:小問集合(高次方程式 図形と方程式 積分 確率 数列 ベクトル) 大問2:関数の最大値(三角関数の置き換え) |
| 2024年 | 大問1:小問集合(有理化 整数 対数関数 余弦定理 確率 数列 極値) 大問2:関数 積分 |
| 2023年 | 大問1:小問集合(解と方程式 領域 余弦定理 関数 数列 整数) 大問2:関数 積分 |
| 2022年 | 大問1:小問集合(有理化 絶対値を含む方程式・不等式 対数関数 数列 確率 ベクトル) 大問2:関数 積分 |
| 2021年 | 大問1:小問集合(指数関数 解と方程式 場合の数 ベクトル 三角関数 数列) 大問2:関数 積分 |
問題構成
試験時間は70分、大問は2つです。
他の科目は年度によって大問の数や傾向が変わることもありますが、数学は一貫しています。
大問1の小問集合では有理化を含む整数問題、解と方程式、数列、ベクトル、余弦定理が頻出です。
大問2は毎年と言っていいほど関数の問題(やそれに続く積分や定義域・閾値の問題)が出題されています。
関数は数Ⅱの履修でカバーできるものになっています。
難易度
試験時間が十分あり、傾向も毎年そこまで変化しないため、易しい部類に入るでしょう。
高得点が良そうされるため、計算ミスは命取りになります。
対策
教科書の章末問題や傍用参考書でパターンが頭に入ったら、手早く計算できるようにしましょう。
理科
化学
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:小問集合(化学基礎 電気分解 気体計算 平衡 コロイド) 大問2:理論小問集合(熱量計算 気体計算 溶解度積) 大問3:無機化学(鉄 亜鉛 アルミニウム) 大問4:有機小問集合(高分子化合物 芳香族化合物 炭化水素) 大問5:有機小問集合(ヨードホルム反応 銀鏡反応 異性体 有機化合物の燃焼) 大問6:有機小問集合(タンパク質 アミノ酸 官能基 キサントプロテイン反応) |
| 2024年 | 大問1:小問集合(炭化水素 金属 気体の発生 芳香族化合物 化学基礎 酸化還元 ハロゲン) 大問2:小問集合(有機化合物の燃焼 気体 溶解度積) 大問3:理論化学(結晶格子) 大問4:理論化学(鉛蓄電池) 大問5:有機化学(芳香族化合物の構造決定) 大問6:有機化学(炭化水素 合成繊維) |
| 2023年 | 大問1:小問集合(化学基礎 熱硬化性樹脂) 大問2:小問集合(化学基礎 金属元素の同定) 大問3:小問集合(水溶液計算 炭化水素の燃焼 電離平衡 気体) 大問4:理論化学(蒸気圧) 大問5:無機化学(カルシウムの化合物) 大問6:有機化学(芳香族化合物) |
| 2022年 | 大問1:小問集合(化学基礎 酸化還元 芳香族化合物の異性体 糖類の還元性 蛋白質 溶解度積 気体の燃焼 電離 炭化水素の燃焼) 大問2:無機化学(アンモニア生成 ハーバー・ボッシュ法) 大問3:無機化学(炭酸ナトリウムの工業的製法) 大問4:有機化学(エステル) 大問5:有機化学(タンパク質) |
| 2021年 | 大問1:小問集合(アルカリ金属 塩 化学基礎 気体 酸化還元) 大問2:無機化学(金属の性質) 大問3:理論化学(硫化水素の電離平衡 溶解度積) 大問4:有機化学(物質の識別操作) 大問5:有機化学(芳香族化合物の分離 構造異性体) 大問6:有機化学(多糖類) |
問題構成
試験時間は60分、大問は5~6個です。
序盤は小問集合として化学基礎の知識をはじめ、各種計算や知識が幅広く問われます。
後半は理論化学や有機化学1つで大問を構成していることが多いです。
年によって若干の変動はありますが、有機化合物のウエイトが大きくなっています。
難易度
理論化学の計算が比較的続くので、不慣れであると時間を取られかねません。
無機化学と有機化学の問題はかなり標準的です。
対策
理論化学の計算と有機化学の知識を重点的に行うと良さそうです。
計算は難しいものを解くよりは、レベルを同じくらいにして、見たことがないタイプの問題がないようにしましょう。
有機化学は炭化水素、芳香族化合物、糖アミノ酸タンパク質、高分子化合物、全て聞かれるので満遍なくやらないと失点につながります。
物理
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:小問集合(力学 電磁気 熱力学 波動(音)) 大問2:力学 大問3:電磁気 |
| 2024年 | 大問1:小問集合(力学 電磁気 熱力学 波動(音)) 大問2:力学 大問3:電磁気 |
| 2023年 | 大問1:小問集合(力学 電磁気 熱力学) 大問2:力学 大問3:電磁気 |
| 2022年 | 大問1:小問集合(力学 電磁気 波動 熱力学) 大問2:力学 大問3:電磁気 |
| 2021年 | 大問1:小問集合(力学 波動(光) 熱力学) 大問2:力学 大問3:電磁気 |
問題構成
試験時間は60分、大問は3つです。
大問1は例年小問集合で、力学、熱力学、電磁気、波動が満遍なく問われます。
原子は直近では出題されていませんが、小問集合で問われる可能性は十分あります。
大問2以降は例年、力学と電磁気で大問1個つづを構成しています。
難易度
問題量に対して試験時間は十分あるでしょう。
出題内容も標準的で、奇抜な問題は少ないです。
直接的な難易度ではありませんが、北里大学の物理は全て選択肢で解答します。
なんとその選択肢が16個近くあることもあります。
計算できたとしても、似たような選択肢を選ばないよう、よく見ましょう。
対策
教科書で公式を抑え、教科書傍用参考書や入試問題集で計算練習を繰り返しましょう。
公式は丸暗記するよりは、次元を意識するなど、導出過程も覚えると良いです。
生物
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:遺伝子発現 分子進化 大問2:遺伝子組み換え技術(プラスミド PCR法 電気泳動) 大問3:植物の環境応答 大問4:光合成 |
| 2024年 | 大問1:生体防御 免疫 大問2:体温調節 呼吸 大問3:ABO式血液型 大問4:花芽形成 長日植物と短日植物 |
| 2023年 | 大問1:血液 ホルモン 赤血球の先天性疾患 大問2:ホメオティック遺伝子 シロイヌナズナ 大問3:生態系 生物のエネルギー利用 窒素循環 森林 バイオーム |
| 2022年 | 大問1:膜タンパク質 細胞骨格 浸透圧調整 大問2:動物の生殖 発生 遺伝(ウニ ショウジョウバエ ヒト) 大問3:化学合成細菌 光合成細菌 進化 |
| 2021年 | 大問1:ラクトースオペロン 大問2:光合成 大問3:神経伝達 ショウジョウバエの行動(脳の神経伝達) |
問題構成
試験時間は60分、大問は3~4個です。
小問集合や知識単体で聞かれるものもありますが、実験を受けての考察問題のウエイトが多いです。
直近では知識のウエイトも増えつつありますが、依然考察問題が重要です。
難易度
試験時間60分に対してはかなりの分量があります。
実験内容を読み、把握する時間も考えると、かなりカツカツでしょう。
対策
知識問題はなるべく早く片付け、実験問題・考察問題に時間を回しましょう。
また実験の結果や実験を受けた結論について問われる問題は、前提知識があればある程度有利に働きます。(ただし、早とちりは厳禁です。)
教科書や資料集を見て、現象やメカニズムだけではなく、それらが発見された背景や関連実験も抑えるようにしましょう。
共通テスト利用方式の特徴と戦略
共通テスト利用入学試験は前期日程の5教科がねらい目です。
確かに3教科方式よりは定員が少ないですが、定員に対して3教科方式よりも多めに合格者が出ていることからも、チャレンジする意味があるでしょう。
【まとめ】北里大学獣医学科で合格を勝ち取るためのポイント
北里大学の獣医学科はキャンパスが十和田にあることもあり、ややアクセスが不便ですが、私立獣医にしては倍率が落ち着いている大学です。
理科は3科目の中から1科目を選択できますが、他の大学で受験したからと言ってその科目に決めつけるのではなく、過去問を見て、自分に合いそうな科目を選択しましょう。
共通テスト利用入学試験も倍率的にはチャンスのある部類に入るので、ぜひチャレンジしてみてください。
-3.png)