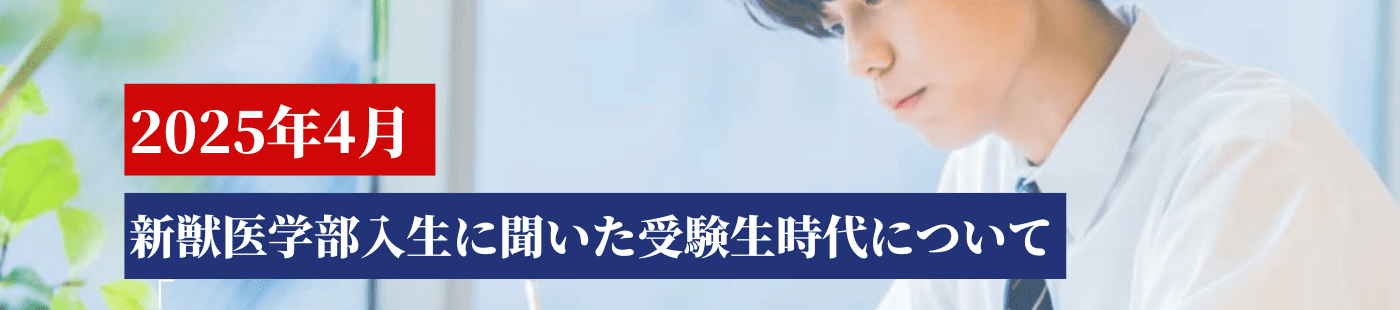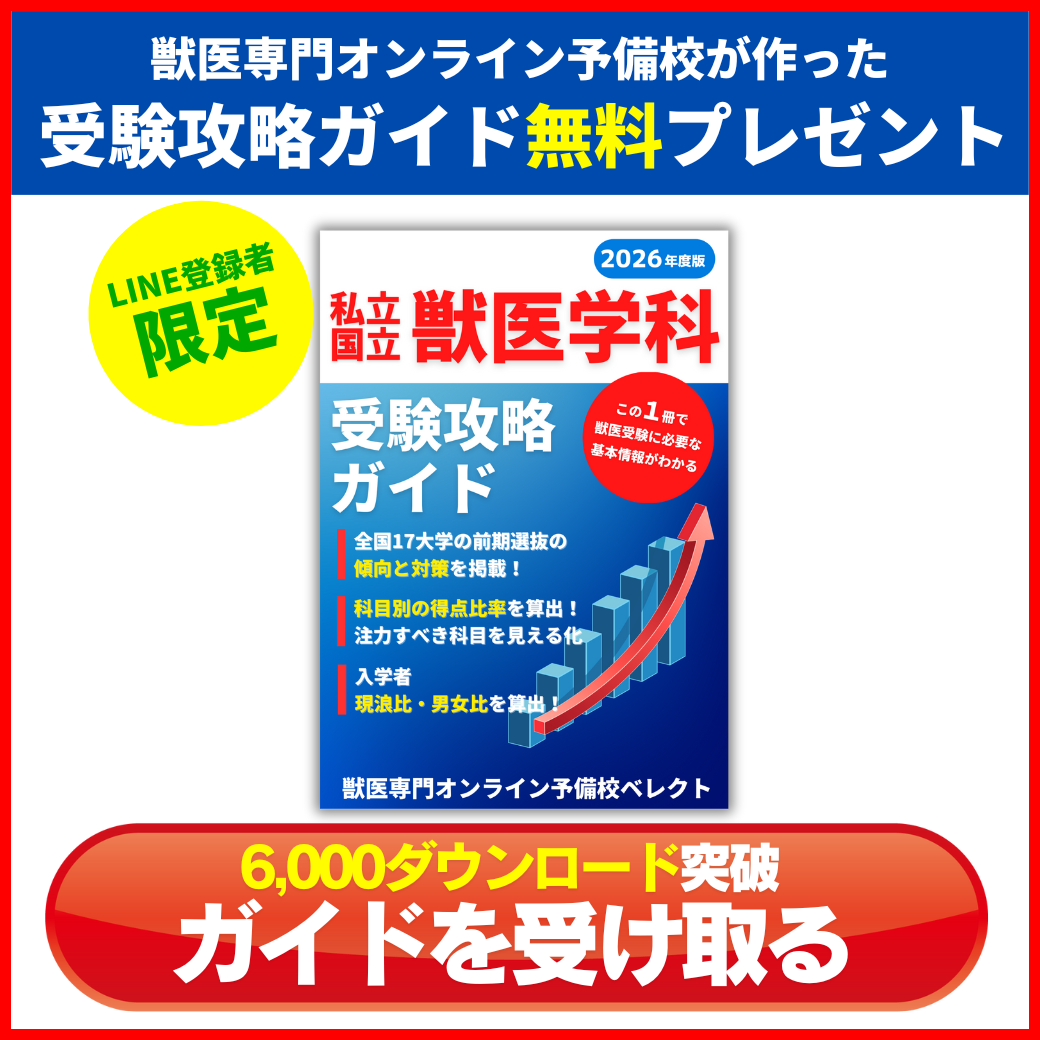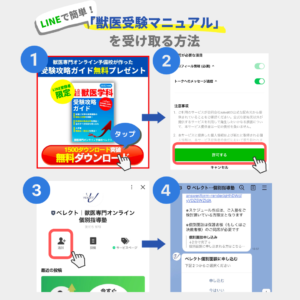こんにちは、獣医専門オンライン予備校のベレクトです。
今回は入学したばかりの2025年度 獣医学部新入生に受験生時代についてのことをいろいろ聞きました!
獣医受験をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 北大生:2名
- 岩大生:1名
- 東工大生:3名
- 北里大生:1名
- 麻布大生:2名
Q.いつ頃から、受験勉強を開始しましたか?
| 開始時期 | |
|---|---|
| 高2 | ・冬(農工大生) ・冬休み後(岩大生) ・2月(農工大生) ・3月(麻布生) |
| 高3 | ・3月(農工大生) ・夏(北大生×2人) |
Q.受験のために塾・予備校に入っていましたか?入塾した時期は?
全員が予備校に通っていました。
| 入塾時期 | |
|---|---|
| 高1 | 北里大生 |
| 高2 | ・1月(麻布生) ・2月(農工大生) ・夏休み(北大生、岩大生) |
| 高3 | 3月(農工大生) |
| 中1 | 北大生 |
| 中2 | 農工大生 |
Q.受験生時代の勉強方法を教えてください
始めた問題集や過去問は必ず3周する。
登下校の電車などでの隙間時間を無駄にしない。
できると思った問題も油断せずにもう一度取り組んでみる(意外と抜けてた知識が出てくる)。
間違えたらその周辺の知識を総復習する。
現役では問題を沢山解くようにしていた。
浪人時代は、予備校の授業を中心にテキストを何回も復習をして答え方を暗記するぐらいまでやった。
高校1、2年までは定期テストでクラス5番以内を目指して勉強し、5位以内をキープ。
高3の3月から映像授業の塾に行きはじめたが、自分で一年間にやる参考書等を決めて塾は主に自習室として利用した。
高校1、2年までは定期テストでクラス5番以内を目指して勉強し、5位以内をキープした。そのおかげで大学受験を本格的に始める前にある程度基礎が出来上がったと思う。
高3の3月から映像授業の塾に行きはじめたが、自分で一年間にやる参考書等を決めて塾は主に自習室として利用した。
農工大の対策をすることしか考えていなかったため、数学は頻出である数3の微積の対策に重きを置き、数学1A2Bは基礎問題精講と共テの実践問題集で対策した。
生物は、図録や教科書を活用して自分で図を描いたり説明できるようにすることを心掛けた。
化学は、最初は苦手だったため自分がよく間違えるポイントをまとめたミスノートを作り、最初はセミナー、次に重要問題集のA問題を解けるようにした結果徐々に農工大の過去問で合格点をとれるようになった。
英語は、学校の授業で様々なレベルの問題を解いていたため、自分では主に単語帳と過去問を使用した。
受ける大学の試験のレベルにもよるが、英単語を完ぺきに抑えれば長文の意味はある程度くみ取れると思う。
国語や地理等の共通テストでしか使わない科目はすぐには身につかなかったので、早めに取り組むほうが後で焦らないで済むと思った。
解説をしっかり読み込んで1回理解したら覚えてなくても演習を繰り返す。
数学の基礎はfocus goldで固め、標準問題はシステム数学錬磨、実戦で固めた。
英語:センター、marchの過去問をしだいに難易度を上げながら週に一回のペースで解き進め、解き終わったら夜に音読、わからなかった単語、表現を完全に理解するまで直しをした。
塾、学校の授業ではwrite to the point,ドラゴンイングリッシュ、京大阪大などの過去問を解いて、入試対策というよりも英語の力そのものを高めた。単語帳はターゲット1900,ターゲット1000
生物:塾のテキストのみで基本的に対策。塾の記述用問題集を3周し、週に4000字程度の記述練習をした。理論から理解することを意識した。
化学:セミナー化学で基礎を固めて、夏休みに化学の新体系で化学を完成させた。無機化学のみは12月に完成させた。計算が遅い分有機、無機化学を誰よりも伸ばした。
国語:共テ対策は過去問が基本。古文単語は古文単語315を使用。登下校の歩いている時間に単語帳を見ながら覚えた。
地理:地理の黄色本を10月ごろから始めて対策。
生活リズムを学校に通っている時と同じにする。
数学→予備校のテキストを完璧にした。すぐにできた問題には◯、時間がかかたものには△、解けなかったものには✕をつけて、△と✕がなくなるまでやった。
生物→まずは映像授業でノートをとって理解した。
真っ白な紙にノートに書いた図を1から再現する練習をした。それができるようになったら問題を解く。
英語→授業以外は毎日一定のルーティーンで取り組むようにした。単語100語、長文音読1つ(同じものを何度も読む)、文法問題集(Engage)を1分野。
暗記事項は漏れなく全部覚え、なるべく本質理解に努めた。
例えば,数学では解いた問題を抽象的に見返すことで「あの問題と本質的には同じ解き方だ!」など
毎週のtodoリストを作っていた(変に盛り込みすぎちゃう節があり総崩れする事がよくあったため最低限やらなければならないことのみ)。
スタプラを記録していたことでどの教科がやっていないかを可視化できた。単語帳は獣医は一冊で良い使い古す。
過去問などで知らない表現や単語が出てきた時にはわからなかったものを書き出すノートに足していっていた。これを受験ちょい直前期(十月ごろ)からやり込んで出そうな表現は覚えていた。
生物はノートをつくり、脳の構造や一度書かなければ覚えられそうも無いもの、過去問に出てきた事項など。文章(オレンジペン)文章とかいて何度も何度も繰り返し読んでいた。
1日を有意義に過ごせるように、翌日のスケジュールを前日の夜に決めるようにしていた。
Q.獣医学部受験におけるおすすめの勉強法を3つ教えてください
- 生物は授業ノートや図表を1から再現する練習
- 英語長文の音読
- 科学に関するニュースを確認し、解決方法や利用方法を考える
- 生物は授業ノートや図表を1から再現する練習をする。
知識が点ではなく全体的な流れで覚えられる。 - 英語長文の音読。長文読解で読んだ文を頭で和訳しながら何度も音読する。
単語やイディオムを覚えられるし、文構造を意識しながら読むことで、英語を英語の語順のまま読めるようになる。音読することで記憶に残りやすくなる。 - 推薦対策として、科学に関するニュースを確認し、毎日1つのトピックに対し政治家、研究者、獣医師になったつもりでどういう解決方法や利用方法があるか考える。
- 生物を落とさない
- 数学を得意教科にする
- 戦略をしっかり立てて勉強
- 生物を落とさない
獣医学部を受ける人たちは大体生物が得意な人が多いので生物選択で受験する場合は基本的な用語問題を落とさないのはもちろん、記述問題や図を描いて説明する問題の対策も万全にする必要がある。 - 数学を得意教科にする
獣医学部受験で合否を分けるのは数学の出来だと思う。ただ、獣医学部の数学は大学によるとはいえ標準的な問題が多く、高得点勝負になると思うので青チャート等の参考書を完ぺきに仕上げることが大切だと思う。 - 戦略をしっかり立てて勉強する
〇月までどの参考書をやるか等の受験全体の戦略だけでなく、入試問題を解く順番や時間配分を守って解くことが高得点勝負の試験を乗り切るには重要だと思う。
- 基礎が完璧になってから応用問題へ
- 志望校よりレベルが高い大学の難易度の勉強
- 答えを写さない(勉強は考えるプロセスが最も重要)
- 共通テスト対策をとにかく早く始める
- 基礎問題を95%解けるようにする
数学ならチャート、科学ならセミナーなどの網羅系を早めから始めておく - 配点、選択科目をしっかり調べ、教科の優先順位をつける
- 英語は、marchの過去問を解きまくる
- 数学は、focus goldの問題でわからない問題を0問にする
- 生物は、用語を入れたら、記述をひたすら練習
- 生物ではとにかく用語を全部覚る
- 基礎をしっかりやる
- ※過去問による勉強は勧めません
獣医学部、特に私立の問題は学習素材としては良問だとは言えないものが多いので、良問を集めた参考書や、問題集で本質的な力をつければクセのある問題も解けるようになります。
- とにかく基礎基本を完璧にする
例) 英語:単語熟語文法 - 授業をしっかりと聞く
- 覚えるべきものはすぐに覚え、演習に時間を費やす
- 過去問をとにかく数こなす
- 理科に関しては記述問題を解く
- わからない単元があったらメモ帳に書きだす
- 網羅系問題集を何回も繰り返す
- 過去問を何回も解く
- 他人に自分が習ったことなどを教え、自分で完全に理解できるようにする
Q.勉強する上で工夫したこと、意識したことはありますか?
どんな時でも自分は挑戦者であり、どの受験者よりも劣ってるという意識を忘れずにいることで一分一秒無駄にできないという必死さを大事にした。
情報の取捨選択も大切。
「勉強できるあの人がこう言っていっていた」からといって、その参考書や勉強法が自身に合っているか、獣医学部への受験に必要なのかを見極める。
自分でそれがわからなければ聞きにいくことを重要視していた。
量も質も追及する。
量より質という言葉もあるが、数学や生物の記述問題は何度も同じ問題に取り組むことで身につく。
問題を解いて丸つけをして終わらせるのではなく、私は青ペンで自分がどこを間違えたのか、自分に何が足りなかったのかを書き足すようにしていた。
あとからそのノートを何度も見返して復習することで、また同じミスを繰り返すのを防ぐことができた。
授業でさりげなく先生が言ったことを必ずメモする。
見るだけではなく書いて覚える。
計算をする時は素早くかつ、0や6などを見間違えないようにできるだけ丁寧に書く。
昨日解けなかった問題が今日は解けているという実感を強く持つ。
家族はもちろん友人知人にも獣医を目指すことを報告して外堀を埋める。
わからなかった問題をわかるようにする。
人に説明できるかどうかがわかったの基準。
暗記に頼らず本質理解に努める。
パターン暗記より、急げば回れです。
やることリストを作る。繰り返しやる。時間をかけてじっくりやる。
1ヶ月後にもう一度覚えてるかチェックする。
自分に合った参考書を選ぶこと。
買って分かりにくかったり、レベルに合ってなかったらすぐやめる。
Q.勉強へのモチベーションはどのように保っていましたか?
- 大学に入ってからしたいこと、行きたいところ、欲しいものを全て紙に書き出し、勉強前に見ていた
- 家族、友人知人に獣医を目指すことを報告して外堀を埋めた
- 適度にYouTubeやテレビを見る。よく寝る。
- 友達とたくさん話す
- 浪人したくない!という思いで勉強
- 気分転換にコンビニで甘いものを買いに外に出る
- お風呂で息抜き
- 大学生になった自分を想像したり、大学生活を想像
- 友達とビデオ通話を繋ぎながら勉強
- 合格後にすることをリストアップ
- 趣味を制限しすぎない
- 直前期以外は1、2時間は趣味の時間を取る
Q.受験勉強をしているとき、親御さんにしてもらって
嬉しかったこと、感謝していること
- お弁当を作ってくれた
- 模試の成績があまり良くなくても、責めないでくれた
- 遅く帰っても、暖かい夜ご飯が並べてあった
- 送り迎えをしてくれた
- 朝早くに起きて必ず見送ってくれた
- 共テのお弁当の中に応援メッセージが入っていた
- 塾に通わせてくれた
- いい成績をとると褒めてくれた
- 試験前からたくさん調べて、下宿を決めてくれた
- 受験の日は外まで見送ってくれた
- 母が受験の時の昼ご飯に毎回メッセージカードを入れていてくれた
- 毎朝起こしてくれた
嫌だったこと、してほしくなかったこと
- 自分で決めた勉強について口出しされたこと
- 勉強している時に、部屋に入ってくること
- 模試や合格発表の時に、何度も自分に声をかけてきたこと
- スマホを見過ぎだと言われたこと
- 自習室から帰ると必ず、勉強の進捗具合を聞いてきたこと
- 参考書代を惜しんで買えなかったこと
まとめ
今年受験を経験した学生のリアルな声をお届けしました。
少しでも受験勉強の参考になれば幸いです。
-3.png)