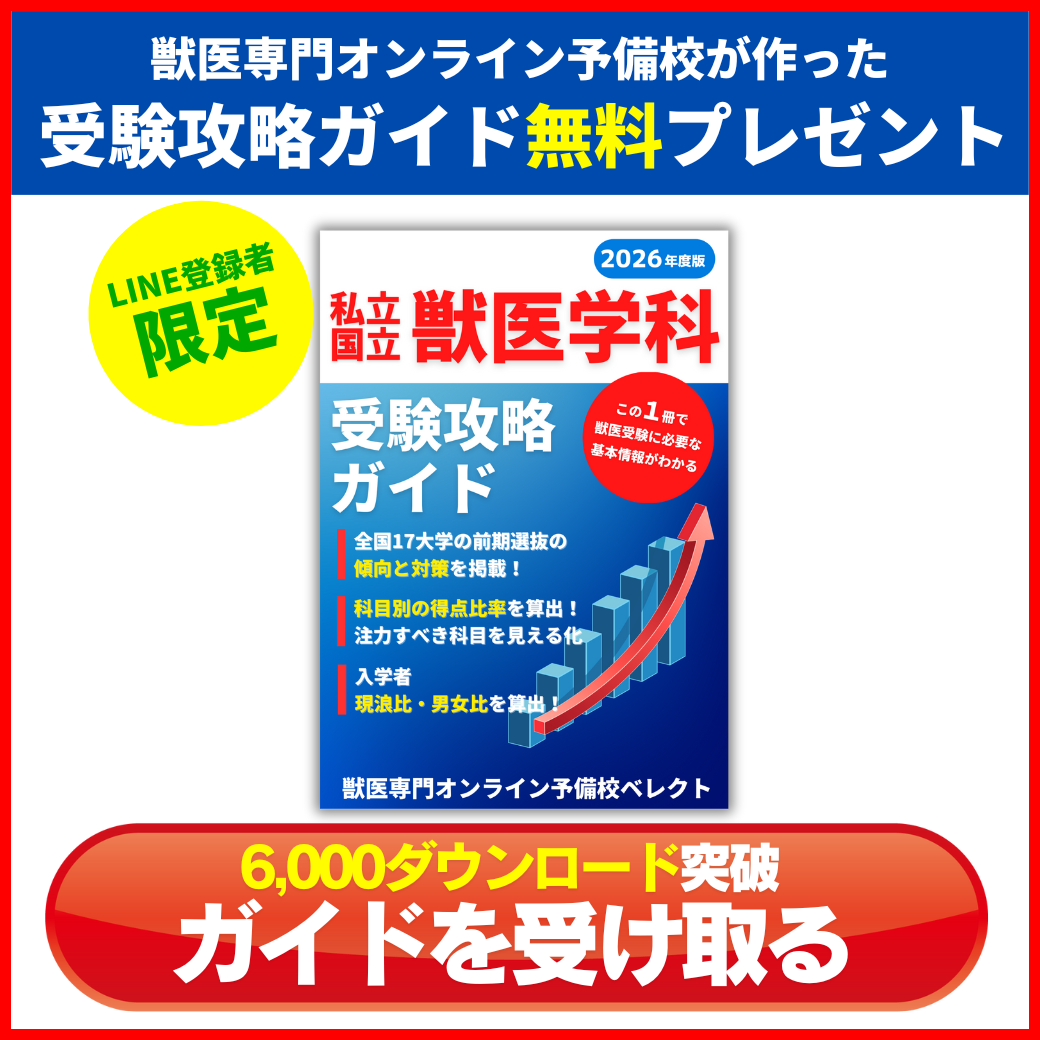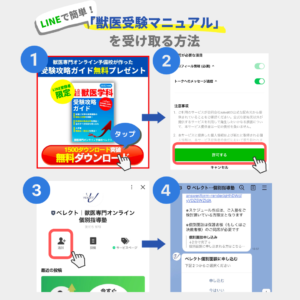こんにちは!獣医専門オンライン予備校のベレクトです。
2026年度・北海道大学獣医学部の一般選抜に向けて、合格点の目安や教科ごとの傾向が気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、北大獣医学部の一般選抜において求められる得点ラインや、英語・数学・理科の出題傾向について、過去問と合格点の分析をもとに詳しく解説します。
担当するのは、当塾講師として受験指導に携わる現役の獣医学部生。
自身の体験をふまえながら、効果的な勉強法までわかりやすくお伝えします。
北大獣医学部を目指す受験生は、ぜひ参考にしてください!
- 前期
- 共通テストの点数が大きなウェイト
- 個別学力試験で試験が実施されない社会・国語は、英語・数学・理科に比べて点数の圧縮率が大きい(共通テストの文系科目でいかに点数を取るかが重要)
- 2026年度からは情報が得点に入るように(15点、されど15点)
- 後期
- 前期試験に比べて、さらに共通テストのウェイトが大きい
- 面接も500点中200点と大きな割合を占めており、面接対策も重要
- 北大獣医学部は1年生の成績によって総合理系入試の人が5名移行→最終的に1学年20+15+5=40名となる
- 各科目の入試傾向と勉強法を解説しました(2019年度~)
北海道大学 獣医学部 3年生。当予備校の講師として活躍中。
前期試験で現役合格(共通テストで8割超え)を果たし、ベレクトは数学・生物・化学・英語を指導。これまでに北海道大学など、複数の獣医学部合格者を輩出しています。
自身の受験経験と豊富な指導実績をもとに、最新の入試傾向の分析や、実践的な勉強法について、当サイトのコンテンツ執筆にも携わる。
(2025年 執筆時)
2026年度 北海道大学獣医学部「一般選抜」の入試科目・必要科目おさらい
最初に一般選抜前期および後期について見ていきましょう。
一般前期
| 内容 | |
|---|---|
| 募集人数 | 20名 |
| 第1段階選抜 | 6倍(倍率が6倍を超えた場合足切りが行われることがある) |
| 試験内容 | ・共通テスト:6教科8科目 ・個別学力試験:3教科4科目(数学、外国語から1科目、理科から2科目) |
| 共通テストの科目 | (315点満点) 【社会】100点×0.4=40点 【国語】200点×0.4=80点 【外国語】200点×0.3=60点 ※英 独 仏 中 韓から1科目 【数学】200点×0.3=60点 【理科】200点×0.3=60点 ※物理 化学 生物 地学から2科目 【情報】100点×0.15=15点 |
| 個別学力試験の科目 | 3教科4科目(450点満点) 【数学】数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B、C(150) 【理科】「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」生物基礎・生物」から2つを選択(150) 【外国語】「英語」「ドイツ語」「中国語」から1つを選択(150) |
共通テストの点数が大きなウェイトを占めていることがわかります。
特に個別学力試験で試験が実施されない社会、国語は英語、数学、理科に比べて点数の圧縮率が大きいです。
そのため理系とはいえ、共通テストの文系科目でいかに点数を取るかが重要になります。国語や社会などなど1問落とすと失点が大きい科目は気を付けましょう。
また、情報が共通テストに追加された2025年度は北海道大学は情報は受験必須とするものの、得点にはいれていませんでした。
しかし2026年度からは15点ではありますが、情報が得点に入るようになりました。されど15点ですが獣医学部は1点2点を争う世界なので侮らずしっかりと勉強しましょう。
一般後期
| 内容 | |
|---|---|
| 募集人数 | 15名 |
| 第1段階選抜 | 6倍(倍率が6倍を超えた場合足切りが行われることがある) |
| 試験内容 | ・共通テスト:6教科8科目 ・個別学力試験:理科から2科目 ・面接 |
| 共通テストの科目 | (465点満点) 【社会】100点×0.5=50点 【国語】200点×0.5=100点 【外国語】200点×0.5=100点 ※英 独 仏 中 韓から1科目 【数学】200点×0.5=100点 【理科】200点×0.5=100点 ※物理 化学 生物 地学から2科目 【情報】100点×0.15=15点 |
| 個別学力試験の科目 | 1教科2科目 面接(500点満点) 【理科】「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」生物基礎・生物」から2つを選択(300) 【面接】(200) |
前期試験に比べて、さらに共通テストのウェイトが大きくなります。前期とは異なり、情報以外は0.5掛けの得点となります。
また面接も500点中200点と大きな割合を占めており、筆記試験だけでなく面接対策も重要となります。専門知識を沢山持っている必要はありませんが、時事ニュースなどには敏感になっておきましょう。
なお北大の獣医学部は1年生の成績によって総合理系入試の人が5名移行するため最終的には1学年20+15+5=40名となります。
【分析】合格にはどれくらいの得点が必要?
北海道大学が発表している、2021~2025年の合格最低点・倍率は以下の通りです。
| 年度 | 合格最低点・合格倍率(受験者数/合格者数) | 共通テスト素点平均 |
|---|---|---|
| 2025年 | 【一般前期】 合格者最低点:591.9/ 750 合格倍率:4.1倍 【一般後期】 合格者最低点:736/950 合格倍率:倍 | 【一般前期】802.55/1000 【一般後期】777.93/1000 |
| 2024年 | 【一般前期】 合格者最低点:621.00/750 合格倍率:4.1倍 【一般後期】 合格者最低点:726.00/950 合格倍率:4.9倍 | 【一般前期】791.09/900 【一般後期】770.60/900 |
| 2023年 | 【一般前期】 合格者最低点:549.15/750 合格倍率:4.2倍 【一般後期】 合格者最低点:700.50/950 合格倍率:4.1倍 | 【一般前期】785.18/900 【一般後期】746.40/900 |
| 2022年 | 【一般前期】 合格者最低点:555.00/750 合格倍率:3.8倍 【一般後期】 合格者最低点:757.00/950 合格倍率:4.8倍 | 【一般前期】753.64/900 【一般後期】722.86/900 |
| 2021年 | 【一般前期】 合格者最低点:592.65/750 合格倍率:3.9倍 【一般後期】 合格者最低点:725.50/950 合格倍率:2.7倍 | 【一般前期】799.82/900 【一般後期】781.27/900 |
倍率について
- どの年も前期後期ともに倍率が4~5倍前後になっていることが分かります。
- 定員は前期が20名、後期が15名ですが、毎年前期では22名が合格しており、少し多めに採られています。後期は定員きっかり15名で採られています。
- 北大は定員に対して倍率が6倍を超えると第1段階選抜(いわゆる「足切り」)を行うことがあると募集要項に書いてありますが、2021年以降では前期後期ともに行われていないと考えて大丈夫です。
- 後期日程はデータによっては志願者数/定員数を倍率としているものもあるため、高い印象を受けがちですが、受験者数/合格者数でみると5倍以下です。後期は前期で合格した人が受験しないので、実質倍率が低くなります。とはいえ、依然高い倍率ですね。
合格最低点について
- 合格最低点は年によって変動が見られます。例えば2022年は共通テストの数学ⅠAが難化したため、受験生全体の共通テストの点数が低くなりました。2023年では同じく共通テストの理科において得点調整が行われましたが、それでも生物選択と物理選択の間で得点差が生じています。
- 個別試験においても数学や物理の難易度に変動があり、特に数学が比較的易しかった2021年や2024年と数学が難化した2022年と2023年では合格最低点に40点以上の差があります。
共通テストを受けた後の出願について
- 先ほど紹介したとおり、共通テストで高得点を取ることはアドバンテージとなるでしょう。
- 大半の受験生は共通テストの受験生が終わると大手予備校のリサーチを利用して出願の参考にされると思います。
北大獣医の場合はボーダーがとても高くまた、A帯B帯C帯に大きな得点差があるかというとそうでもなく、僅か数点の差で判定が悪くなることもあります。
- また北大の個別試験はどちらかと言えば高得点を取りに行くものなので、共通テストで作ったアドバンテージが二次試験でひっくり返ることは十分起こりえます。
例えば、共通テストの素点で30点差が付いたとしても、実際は点数が圧縮されるので9点~12点差ですね。10点の差は英作文での減点やちょっとした計算ミスであっという間に埋まってしまいます。
- そのため共通テストのリサーチが悪かったからと言って一概に出願を見送るのは少し待ってください。
大事なのは自分が共通テストに強いのか、二次試験に強いのか歴代の模試の順位や偏差値を参考に見極められるようになっておくことです。共通テスト逃げ切り型の人もいれば、二次試験後追い型の人もいてそれは人それぞれです。
- 実際北大生に聞くと、共通テストの判定は散々だったが合格することができたという声をよく耳にします。
【勉強法】過去問などから入試の傾向と対策を解説
ここからは各教科の出題傾向とそれに合った対策・勉強法を解説していきます。
数学(前期のみ)
北大の数学の出題傾向、問題構成は以下のようになります。
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:数列 大問2:平面上の曲線 大問3:積分法 極限 大問4:複素数平面 大問5:整数 |
| 2024年 | 大問1:図形と方程式 大問2:確率 大問3:数列、積分法 大問4:ベクトル 大問5:微分法、積分法 |
| 2023年 | 大問1:複素数平面 大問2:ベクトル 大問3:微分法 大問4:確率 大問5:微分法、図形と方程式 |
| 2022年 | 大問1:整数 大問2:ベクトル、漸化式 大問3:積分法 大問4:確率 大問5:複素数平面 |
| 2021年 | 大問1:ベクトル 大問2:微分法 大問3:微分法 大問4:数列、数学的帰納法 大問5:積分法、媒介変数表示 |
| 2020年 | 大問1:ベクトル 大問2:図形と方程式、整数 大問3:確率、整数 大問4:数列、微分法、極限 大問5:積分法、極限 |
| 2019年 | 大問1:ベクトル 大問2:整数 大問3:微分法、図形と方程式 大問4:確率 大問5:積分法、数列 |
北大の数学は大問5つからなり、試験時間は120分です。5問とも途中計算も含めて提出します。答えが一致していも過程の証明や方法の不備があると減点されるので日頃から丁寧に解答を作るよう心がけましょう。
従来の北大数学の特徴として、「ある程度の難易度の問題を確実に得点する」ことが挙げられていました。一般の国立大学に比べて、誘導も多く、教科書や参考書をしっかりとやっていれば高得点が狙えるのが特徴です。
傾向がつかみにくくなっている
しかし、近年では難易度が上がる(2022年と2023年が顕著)ことも易化する(2024年)こともあり、傾向がつかみにくくなっています。対策として、問題の難易度を選り好みせず、幅広く練習することが必要です。
分法、積分法は計算ミスをせず最後まで解き切ることが合格のカギ
難易度には変動が見られますが、ベクトルや微分法、積分法、極限、数学、確率が毎年のように出題されており、これらの単元を克服することが重要だと言えます。特に微分法、積分法は計算ミスをせず最後まで解き切ることが合格のカギとなります。また「整数」は2025年度の共通テストの範囲からは外されましたが2025年度の二次試験で出題されたためしっかりと勉強しておきましょう。
外国語(前期のみ)
英語
北大の英語の出題傾向、問題構成は以下のようになります。
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:読解・英作文 大問4:会話文 |
| 2024年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:読解・英作文 大問4:会話文 |
| 2023年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:読解・英作文 大問4:会話文 |
| 2022年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:読解・英作文 大問4:会話文 |
| 2021年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:読解・英作文 大問4:会話文 |
| 2020年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:読解・英作文 大問4:会話文 |
| 2019年 | 大問1:読解 大問2:読解 大問3:読解・英作文 大問4:会話文 |
北大の英語は大問4つから構成され、傾向難易度ともに毎年変わっていません。英語が一番対策しやすいとも言えるでしょう。
試験時間は90分で、大問4つを解きかつ見直しをするとなるとなかなかタイトであることが分かります。
読解問題は2題出題され、和訳、正誤選択、空欄補充などを素早く正確に行う必要があります。
大問3の読解・英作文問題は、100語前後の英作文
大問3の読解・英作文問題ではテーマに即して100語前後の英作文が課されます。ここで重要なのは難しい文法を使いこなすことではなく、複数形や時制、冠詞、前置詞、をミスなく用いることです。実際に学校の先生や塾の先生に添削してもらうとよいでしょう。
大問4の会話文では登場人物が会話を行い、その要約を語群から埋める形式で出題されます。選択肢もかなりひっかけが多いのでなんとなくではなく、内容と文法の両方向から正解を絞り込む必要があります。
理科(前期・後期)
化学
北大の化学の出題傾向、問題構成は以下のようになります。
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:理論化学 大問2:無機化学 大問3:有機化学 |
| 2024年 | 大問1:理論化学 大問2:無機化学 大問3:有機化学 |
| 2023年 | 大問1:理論化学 大問2:無機化学 大問3:有機化学 |
| 2022年 | 大問1:理論化学 大問2:無機化学 大問3:有機化学 |
| 2021年 | 大問1:理論化学 大問2:無機化学 大問3:有機化学 |
| 2020年 | 大問1:理論化学 大問2:無機化学 大問3:有機化学 |
| 2019年 | 大問1:理論化学 大問2:無機化学 大問3:有機化学 |
北大の化学は大問が3つありますが、各大問はⅠ、Ⅱ2つの中問に分かれています。ⅠとⅡは全く独立した問題なので大問丸々総崩れということは起きにくいです。理科は2科目で150分であるため、1科目に割ける時間はおおよそ75分、中問1つあたり約12分です。
大問1が理論化学、大問2が無機化学、大問3が有機化学と大分されますが、無機化学と理論化学など融合問題も多く見られます。特定の分野を苦手とすると足枷になってしまいます。
部分点はなく、有効数字や構造式の少しのミスもバツ
解答形式は、基本的に数値、化学(反応)式や図示で、途中計算は採点官に見られません。部分点はなく、有効数字や構造式の少しのミスもバツになってしまうので気をつけましょう。
全体として解きやすい問題が多いですが、難易度は問題によって差が大きく、試験時間が短いので自分が確実に得点できる問題を解きにいくことがとても大切です。
物理
北大の物理の出題傾向、問題構成構成は以下のようになります。
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:力学 大問2:電磁気 大問3:波動 |
| 2024年 | 大問1:力学 大問2:電磁気 大問3:波動 |
| 2023年 | 大問1:力学 大問2:電磁気 大問3:熱力学 |
| 2022年 | 大問1:力学 大問2:電磁気 大問3:波動 |
| 2021年 | 大問1:力学 大問2:熱力学 大問3:電磁気 |
| 2020年 | 大問1:力学 大問2:電磁気 大問3:熱力学 |
| 2019年 | 大問1:力学 大問2:電磁気 大問3:熱力学 |
北大の物理も大問3つから構成され、大問の中に中問があります。力学と電磁気は必ず出題され、残りの1つは波動か熱力学になります。原子はほとんど出願されませんが捨てるのはやめましょう。
解答形式は基本的に穴埋め
解答形式は基本的に穴埋めですが、時々論述問題が出題されます。2023年には熱力学もおいて従来にはなかった大きな論述問題が課されました。
難易度はそこまで高くないが、、、
難易度はそこまで高くないと言われていますが、理科全体でかけていい時間を鑑みると素早く正確に解く処理力が重要になります。また公式を丸暗記するのではなく、公式の導出過程に関する理解も必要でしょう。
獣医は生物系ですが、物理で受験する人もいます。正式な統計は公表されていませんが、生物選択が多いものの物理選択も決して少数派ではありません。
私個人の感覚としては専門科目の勉強において物理選択だから不利になるということはないです。
生物
北大の生物の出題傾向、問題構成は以下のようになります。
| 年度 | 問題構成 |
|---|---|
| 2025年 | 大問1:恒常性(血液 免疫 腎臓) 遺伝 大問2:減数分裂 発生 受精 大問3:感覚器 大問4:生態系 |
| 2024年 | 大問1:酵素反応・遺伝子 大問2:代謝・遺伝子 大問3:生殖 大問4:動物の行動・進化 |
| 2023年 | 大問1:発生・遺伝子 大問2:遺伝子・生殖 大問3:内分泌系 大問4:進化 |
北大の生物が大問4つから構成され形式は用語、記号選択、論述問題です。分量が多いため、他の理科もう1科目の所要時間との兼ね合いが重要です。
毎年のように遺伝、生殖、進化が出題
分野としては、毎年のように遺伝、生殖、進化が出題されています。遺伝や生殖は苦手意識を持っている受験生が多く、進化は理解が浅くなりがちな単元なので、これらの単元を得点源とすると有利になるでしょう。
難易度は特段高くないが、、、
難易度は特段高くありませんが、分量が非常に多く知識などパパっとできる問題を捌いて遺伝などの計算や論述に時間を残す必要があります。そのためには教科書・資料集レベルの知識を正しく論理的に用いる力が必要になります。普段から自分の言葉で現象や仕組みを説明できるよう練習を積むことが合格につながります。
詳しくは別の記事でご紹介しますが、北大の理科は北大にゆかりのある先生の功績が問題としてしばしば取りあげられています。特に木原均先生のパンコムギの研究に関連したゲノムの問題は過去何度も出題されています。
まとめ
北海道大学獣医学部の一般選抜における入試の傾向、対策、勉強方法についてご紹介しました。
北大の獣医は難易度が高いことで有名ですが、傾向や対策を知ることでなぜ難しいと言われているのか、自分は何が足りていないかを客観的に判断することができます。
北大は高校の学習で十分対処できる問題が出題されます。
普段から地道に基礎を積み重ねることが合格へつながるでしょう。
本記事が受験生の方々の参考になれば幸いです。
-3.png)
.jpg)