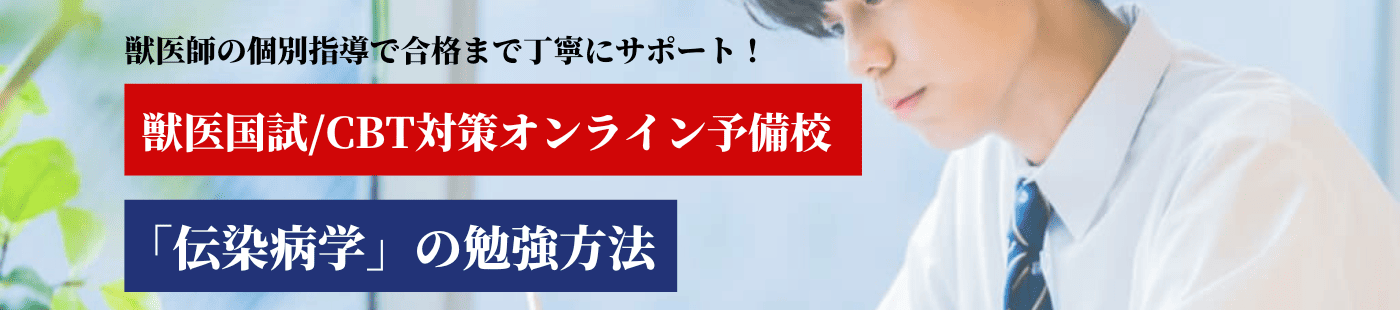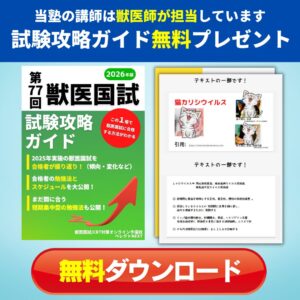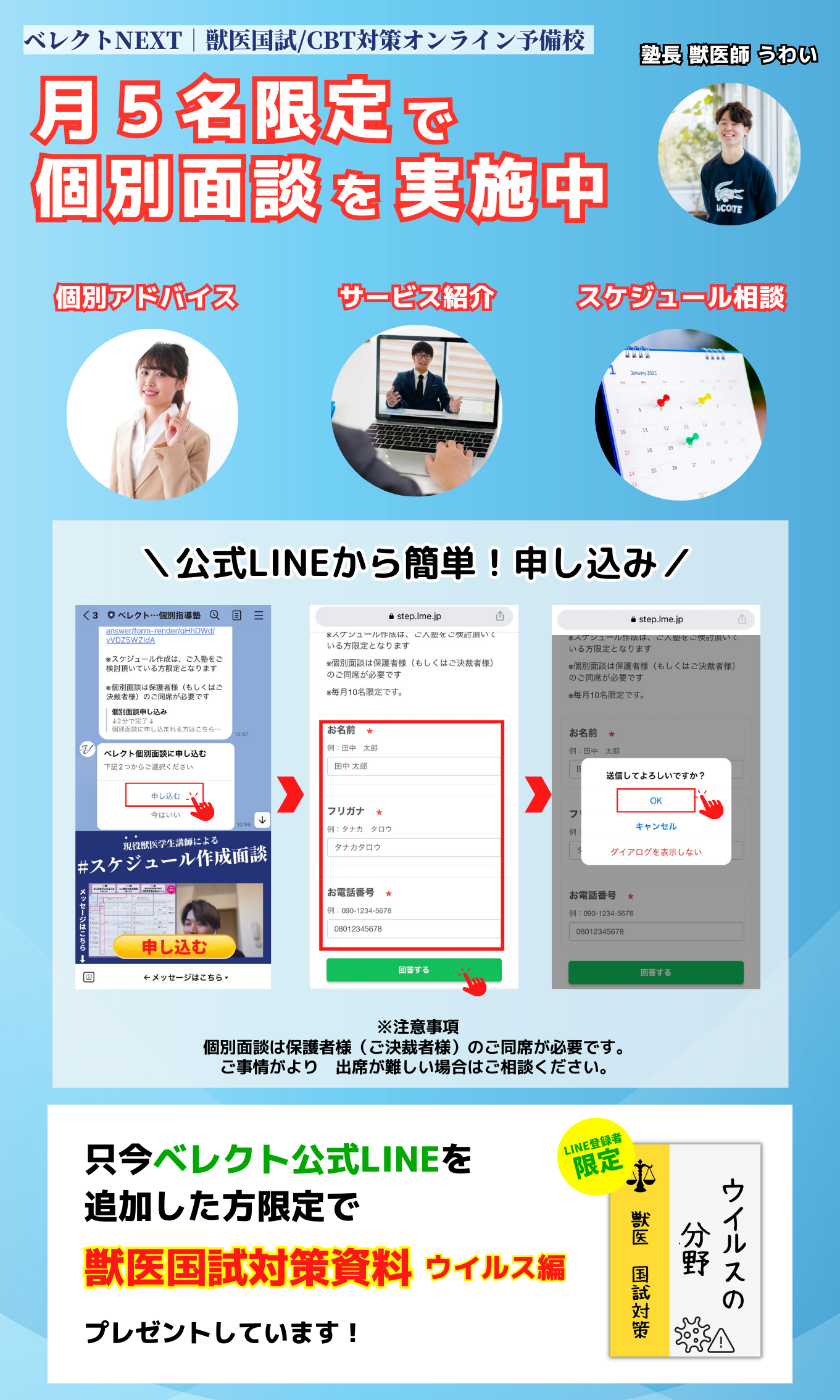こんにちは、ベレクトNEXTです。
伝染病学は独立した学問というよりも、微生物や寄生虫の”疾患”を扱う学問という側面が強いです。
そのため、これらの学問を先にしっかり勉強しておけば問題もかなり解きやすくなります。
一方で、これらの学問と異なるところは、写真がより重要であり、種差や検査法を意識することが多いということです。
このページでは、獣医師国試「伝染病学」の勉強方法と大事なことを解説しています!
ぜひ参考にしてみてください。
伝染病学の勉強方法
先に微生物学や寄生虫学などの復習を
伝染病学は、微生物学や寄生虫学の知識がベースとなるため、これらを一通り学んだ後に勉強するのが最も効率的です。
不安がある人は、これらの科目を先に勉強しましょう。
麻布カラーアトラスなどで罹患動物の外貌や病理組織写真をよく見ておく
伝染病はC,D問題でもよく出題される科目の一つです。
疾患ごとに罹患個体の外貌や病変の写真、病理組織像などは必ずチェックしておくようにしましょう。
そのほかにも、年度別の発生件数や分布図などの形でグラフや図が出題されることもあるので、その点も注意しておきましょう。
教科書であれば「動物の感染症」がおすすめ!
国家試験対策としての教科書での学習は、基本的にどの科目でもあまりおすすめしていませんが、伝染病学については「動物の感染症」をおすすめします。
教科書でありながら、各論に掲載されている内容は重要事項ばかりで、疾患ごとに記載されているのがおすすめポイントです。
また、巻頭のカラー写真は過去にそのまま試験問題の写真として使用されたこともあるので一見の価値があるかと思います。
伝染病学の勉強で大事なこと
微生物学や寄生虫学がどれだけ身についているかが最初の鍵
微生物学と伝染病学
微生物学(細菌学・ウイルス学・真菌学)の知識は伝染病を学ぶにあたって必須となります。
伝染病の問題の中には、その疾患が細菌によるものなのか、ウイルスや真菌によるものなのか、それらを区別できることが前提となっている問題も多数見受けられます。
伝染病学を学び始める前に、特に分類の仕方についてはよく復習しておきましょう。
寄生虫学と伝染病学
伝染病学に出てくる疾患に寄生虫疾患はあまり多いとは言えませんが、発熱や下痢など非特異的な症状を示す疾患の区別はできるように違いを意識しておきましょう。
疾患ごとの特徴を抑えて、似た症状を示す疾患との区別ができるように
何の病原体によるものか
その疾患が何の病原体によるものなのか考えることは、検査方法や鑑別疾患を考える上でも非常に重要です。
同じ病原体でも名前や症状が異なることもある
動物や病変を形成する部位によって、病気の名称が変わるということは伝染病学ではよくみられます。
もちろん症状や致死率なども異なるため、それらは個別に覚えなければいけません。
公衆衛生とのつながりも大事
伝染病は、人獣共通感染症や食品衛生とも非常に関わりが深い分野です。
獣医療の領域に留まらず人の健康にどのような影響をもたらすかも考えてみると、なぜその病原体が重要とされているのかがわかるということもあります。
普段からたくさん写真を見るように!
カラーアトラスや教科書、授業スライドの活用
伝染病学は図や写真の理解が特に重要な科目です。
そのため、同じ疾患であってもできるだけ多くの写真を見て特徴をつかんでください。
過去問を解きながら覚えていく
「問われ方が変わると途端に解けなくなってしまう」こういった悩みを抱えている受験生は多いようですが、多くの場合、その原因は問題を解きなれていないことにあるようです。
バラバラの知識がふわっと、頭に入っているだけではなかなか正答には辿りつけません。
できるだけ早い段階で過去問を解いて、バラバラの知識をまとめていきましょう。
最後は語呂に頼るのもあり
どの科目についても言えることですが、理解することが知識の定着につながりますので、早い段階で語呂に頼るのはあまり得策とは言えません。
しかし、時間が限られていたりどうしても覚えられないことがある時には語呂に頼ってしまった方が早い、ということもあります。
微生物学や寄生虫学は似ている複数の用語、病原体名などをまとめて覚えること自体が理解につながるという側面もありますので、ここぞという時には語呂を活用して覚えるようにしてください。
第76回試験の伝染病学について
今年の試験ではどうだったか(傾向や難易度など)
難易度に関しては、難しい問題はほとんどなく、やや易~例年通りの難易度と思われます。
B問題から8問、C問題から3問、D問題から2問出題されました。
来年の予想、対策ポイントなど
76回では、BSEに関する問題のほか、豚熱に関する問題も出題されました。
伝染病学は時事ネタに直結しやすい科目です。頻出の問題については過去問を利用して復習しつつ、感染症の発生状況など最新の情報をチェックしておきましょう。
実際に出た問題を一問解いてみよう!
第76回B問題
1.「家畜伝染病予防法」において家畜伝染病に指定されている。
2. 2018年以降、我が国で毎年度発生している。
3. 病原ウイルスは日本脳炎ウイルスと同じウイルス科に属する。
4. 病原ウイルスは主に蚊が媒介する。
5. 病原ウイルスは扁桃で増殖する
解答:4
解説:
1.「家畜伝染病予防法」において家畜伝染病に指定されている。 正しい。感染力が高く、有効な治療法がないことから家畜伝染病に指定されている。
2. 2018年以降、我が国で毎年度発生している。 正しい。我が国では2007年に清浄化が達成されたが、2018年以降各地で散発的に発生が続いている。
3. 病原ウイルスは日本脳炎ウイルスと同じウイルス科に属する。 正しい。豚熱ウイルスおよび日本脳炎ウイルスはともにフラビウイルス科に属する。
4. 病原ウイルスは主に蚊が媒介する。誤り。 豚熱は感染豚(またはイノシシ)の排泄した唾液、涙、糞尿などの接触により感染が拡大する。5. 病原ウイルスは扁桃で増殖する。正しい。ウイルスは感染後、扁桃で増殖するため、
まとめ
伝染病学は、いわば微生物学と寄生虫学の応用の学問です。
それに加えて、解剖学や組織学、病理学などの知識を活かして診断につなげていきます。
そのため、これらの学問をしっかり学んで、伝染病学の知識に結実させていきましょう。
この記事は、獣医師の鈴木先生が執筆しました。